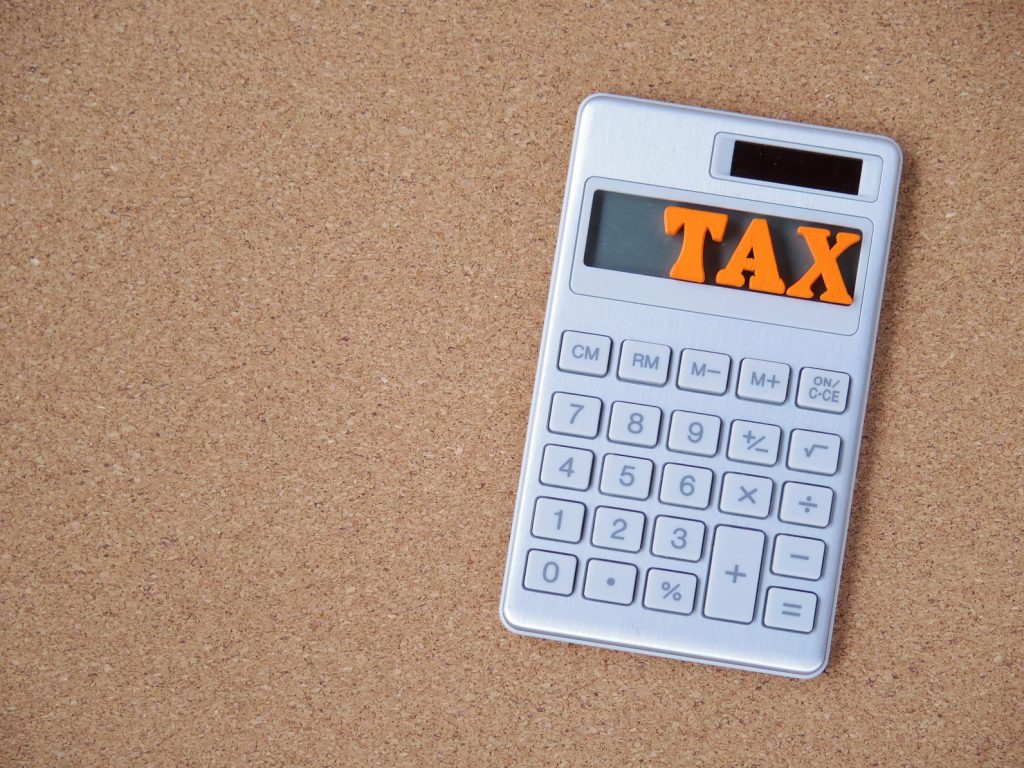個人年金を契約したものの必要性を感じなくなった、あるいは他の商品に乗り換えるために解約したいと考える場合もあるでしょう。今回は、解約する際に税金がかかるのかという点や、解約せずに済ませるにはどうすればよいかという点について解説します。
目次
個人年金保険を解約したらどうなる?
解約返戻金が返金される
大抵の場合、個人年金保険には解約返戻金というものが設定されています。これは、「保険を途中解約した際に、それまでに支払った保険料の一部または全額以上のお金を返金する」という仕組みです。解約返戻金の金額を決定する「返戻率」は保険に加入していた期間や契約内容によって変化するため、解約検討時に確認する必要があります。
早期の解約は損をする
契約後の時間経過に伴って返戻率が高まる保険に加入した場合、早期に解約すると損をするケースもあります。返戻率が100%を超えるのは「保険料の払い込みが完了したり、設定された支払期間を超えたりした場合のみ」という設定になっている保険の場合、早期の解約では元本割れを起こすことになります。
解約返戻金には税金がかかる?
返戻率100%超えで税金がかかり、返戻率100%未満なら非課税
個人年金保険を解約した際、解約返戻率が100%を超えて利益が発生する場合には所得税が課せられます。課せられる税の種類は、20%の源泉分離課税もしくは総合課税のどちらかになります。確定年金タイプの保険について、契約から5年以内に解約すると源泉分離課税が、それ以外の場合には一時所得に該当し、総合課税が課せられます。解約返戻金が100%を下回っている場合、利益は発生していないため非課税となります。
贈与税がかかる場合がある
稀なケースではありますが、個人年金保険の契約者、つまり保険料納付者と解約返戻金の受給者が異なる場合があります。このケースだと、保険料総額と解約返戻金の差額が計上できないため、返戻金の総額に贈与税が課せられます。なお、贈与税は1,100,000円まで非課税となりますが、これは1年間の全ての贈与の総額で、超えた分には税が課されます。
確定申告が必要な場合がある
解約時の返戻率が100%を超えて利益が発生し、かつその金額が200,000円を超えた場合には確定申告を行う必要があります。ただし個人年金保険の返戻率が100%を上回ることはそれほどなく、利益率も低いため利益が200,000円を超えるケースは多いとは言えません。また、一時所得の計算には500,000円の特別控除枠もあるため、解約返戻金に対して確定申告を行うケースはあまり多くありません。
個人年金保険を解約せずに済ます方法
自動貸付制度で支払いを止める
個人年金保険の多くには、自動貸付制度が付いています。これは、保険料の支払いがなかった場合、保険会社が一時的に保険料を立て替える制度です。
保険会社からの貸付総額が解約返戻金を下回っていて、かつ保険料払込猶予期間内である場合であれば、この制度を活用できます。解約返戻金の額や猶予期間は被保険者によって異なる上、立て替え分には利息も課せられるため、制度を利用する前には詳細を確認しておきましょう。
契約者貸付でお金を借りる
自動貸付制度の他に、契約者貸付制度を利用する方法もあります。これは保険会社が契約者に貸付を行う制度です。ただし貸付金額は解約返戻金の一部の額に限ります。貸付金の返済は一括・分割返済どちらでも可能ですが、自動貸付制度と同様に貸付金には利息が発生します。
払済保険で保険の一部だけを残す
個人年金保険は、それまでに支払った保険料を元本として、支払う保険料総額の小さな保険に切り替えることができます。これを、「払済保険」と言います。
将来給付される年金総額の金額は少なくなりますがそれまでの支払保険料を残し、貸付も受けることなく年金保険契約を維持することができます。これまでにある程度の保険料を支払っている場合には、変更後の年金額もある程度確保されます。
個人年金は元本割れのリスクがある?
支払い満了すれば元本割れしない
多くの個人年金保険では、契約時に満期保険金額・保険料・満期返戻率などを決定します。解約返戻金の返戻率もその際に提示されますが、保険料を納める期間が長いほど高く設定される場合が多いと言えます。
そのため全ての保険料を支払えば元本割れを起こすことはほとんどありません。満了まで保険料を払いきれば全額もしくはそれ以上の返戻金を受け取れるケースが多いため、支払満了が間近で解約を検討している場合には一度考え直してみてもよいでしょう。
元本割れするケースもある
中途解約以外に元本割れの理由となるのは、主に3点です。1つ目は、個人年金保険に特約を付加して契約している場合です。特約を付加するとその分保険料は高くなるため、年金部分と合わせた時に元本割れを起こすことがあります。
2つ目は、変額年金である場合です。変額年金は、保険会社の資産運用の結果次第で年金の受取金額が変化するため、運用が不振である場合には返戻率が100%以下になることも考えられます。
3つ目は、保険会社が破綻した場合です。保険会社自体も事業保険に加入してはいるものの、100%の元本が戻ってくる保証があるとは言いにくいでしょう。
まとめ
契約期間の満了前に個人年金保険を解約した場合、返戻金が払込保険料を下回ってしまうこともあります。元本割れを起こすことなく返戻金を受け取りたい際には、この記事で紹介したような方法を検討してみるのもひとつの手段と言えるでしょう。