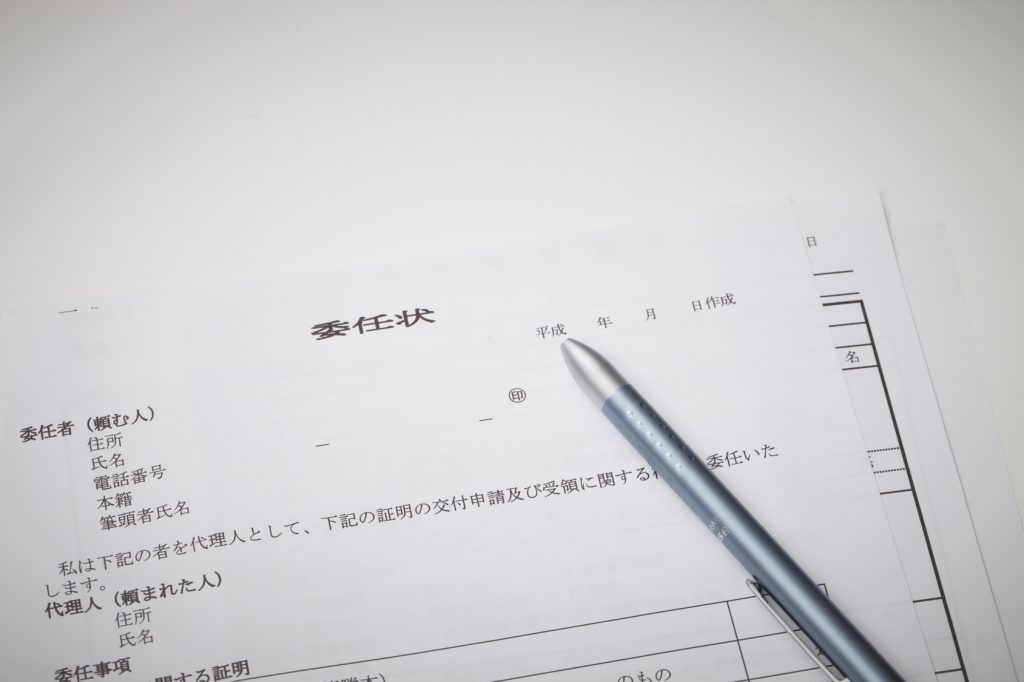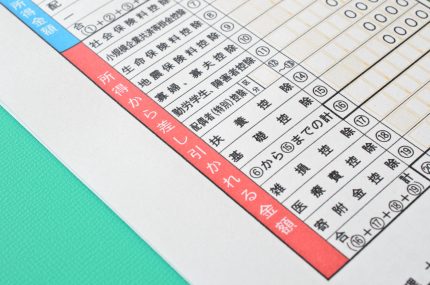保険加入者が日ごろから保険料を納め、病気やケガの治療が必要となったときに支え合う目的で作られたものが公的医療保険制度です。公的医療保険にはいくつかの種類がありますが、この記事では自営業者や無職の人が加入することの多い国民健康保険の加入方法について紹介します。
目次
国民健康保険加入手続きに必要な書類
健康保険の資格喪失証明書
何らかの理由によってそれまで加入していた健康保険を外れるとき、多くの人は国民健康保険に加入することになります。健康保険を外れる理由として、次のような点が考えられます。
勤務先を退職したなどの事由により、加入していた健康保険の資格が無くなったとき
家族が加入している健康保険における扶養対象から外れたとき
健康保険から国民健康保険へ加入し直すときには「資格喪失証明書」が必要となります。「資格喪失証明書」は以前働いていた会社やこれまで加入していた健康保険組合、年金事務所などから発行してもらうことができます。
申請者の個人番号確認書類
国民健康保険への加入手続きができるのは、世帯主・届け出を必要とする本人・住民票で同一世帯となっている人のいずれかです。それ以外の代理人が手続きを行うときには委任状が必要となります(詳細は後述します)。
手続きの際は、世帯主および届け出を必要とする本人の個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)が必要です。加えて、届け出をする人の本人確認書類も必要となります。届出人の本人確認書類は、種類や写真の有無などによって1点で良いものや2点必要なものがあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
その他申請理由に応じて必要な書類
子供が生まれたとき・生活保護の受給を必要としなくなったときなどについても、国民健康保険の手続きが必要です。子供が生まれたときには、個人番号確認書類や本人確認書類の他に保険証と母子手帳を用意します。生活保護の受給を必要としなくなったときには、個人番号確認書類・本人確認書類に加えて保護廃止決定通知書を持参してください。
国民健康保険加入手続きの場所や期間
申請期間は14日以内
会社の健康保険から国民健康保険へ移行する場合、申請期間は「退職した次の日から14日間」と定められています。国民健康保険へ加入する際には、ポイントが2点あります。1つ目は、「申請を行わなくても、退職した次の日からは国民健康保険の加入者扱いになる」という点です。そのため、申請後には健康保険の資格を喪失した次の日まで遡って国民健康保険料を請求されます。
2つ目は、「申請期間を過ぎてからの手続きだと保障を受けられない」という点です。これは、「未申請のまま14日以上が経過した状態で病院にかかると、診察治療費を全額自己負担しなければならない場合もある」ということを意味します。申請期間内であっても、できるだけ速やかに手続きを行いましょう。
役所の管轄窓口にて手続き
国民健康保険への変更手続きは、居住する市区町村役所の窓口で行います(郵送での手続きを受け付けている場合もあります)。窓口名は市区町村によって異なり、申請事由によっても担当する窓口が異なることがあるため、役所内の案内所などで事前に確認するようにしてください。
国民健康保険証はいつ届く?
当日窓口で発行される場合が多い
国民健康保険証は、必要書類をきちんと揃えて窓口で申請すればその日のうちに発行されることもあります。ただし、本人確認書類が不足していたり、代理人が申請を行ったりした場合には郵送となるケースも少なくありません。早期に保険証が必要な人は、一番早く保険証が発行される方法をあらかじめ市区町村の窓口に確認するようにしてください。
自治体によっては後日簡易書留で郵送
即日発行を行わず、世帯主当てに簡易書留で郵送するという自治体もあります。不在が続いて郵便を受取ることができなかった場合、保険証は市区町村の窓口に戻されることとなるため、本人確認資料を持って受け取りに行くようにしましょう。
本人以外が手続きをする場合
代理人が届け出をする時は委任状が必要
前述の通り、国民健康保険への切り替え手続きは代理人が行うこともできます。その場合、委任状を用意しなければなりません。
委任状は、各市区町村のホームページからダウンロードして使用します。世帯主や届け出を必要とする本人が記入しなければならないため、余裕をもって準備を進めましょう。
代理人の本人確認書類を持参する
代理人が手続きを行う場合、代理人の分も本人確認書類を提出する必要があります。公的機関の発行した顔写真付きのもの(免許証・パスポート・個人番号カードなど)を用意します。顔写真のない本人確認書類(保険証など)では手続きができないこともあるため、あらかじめ市区町村の窓口に確認をしてから申請に行くようにしましょう。
代理人申請の場合保険証は後日郵送
代理人が国民健康保険への加入手続きをすると、保険証が即日発行されることは基本的にないと言えます。ほとんどの場合は後日、世帯主当てに簡易書留で郵送されることになるため、確実に受け取れるようにしておいてください。医療機関を受診する予定があり、代理人に手続きを依頼したい人は、早めかつ計画的に準備をしておくことが大切です。
まとめ
国民健康保険への加入手続きについて紹介しました。退職した際などには速やかに手続きを行わないと、医療費を全額支払わなければならなくなる場合も考えられます。手続きを行う人や自治体の方針によっては保険証の発行に時間を要することもあるため、事前に確認をしておくとよいでしょう。