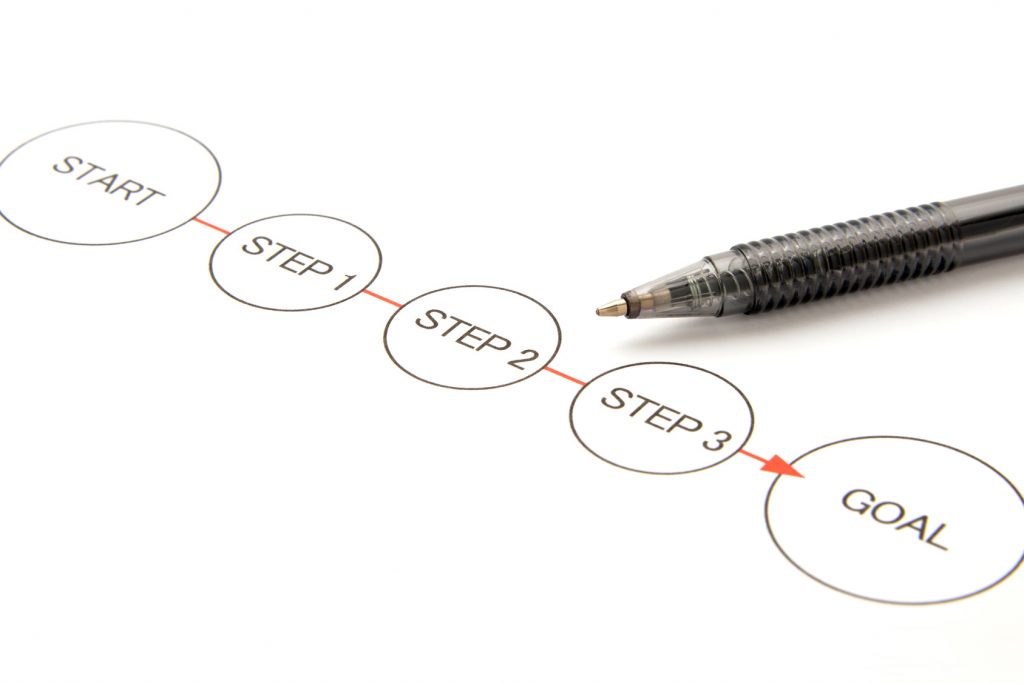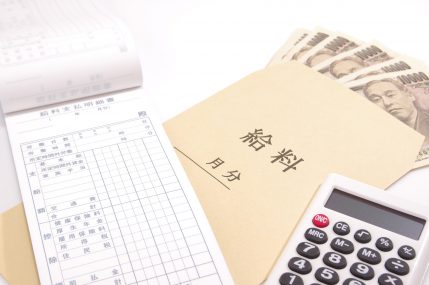勤務先の健康保険に加入している人は、退職時に健康保険証を返却します。健康保険の資格がないと、病院にかかったときに全額自己負担しなければなりません。ここでは退職後の健康保険への加入手続きの方法や注意点について説明します。
目次
退職後の社会保険は?
退職前の保険を任意継続する
「任意継続」とは、退職前の健康保険を2年まで継続できるという制度です。任継続被保険者になるには下記の条件を満たす必要があります。
・退職前の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に手続きをすること
健康診断の補助や保養所の利用など在職中に加入していた健康保険組合の保健事業が充実している場合は、任意継続した方が良いこともあります。ただし、退職前の健康保険を任意継続しても、健康保険料は同額ではありません。在職中は事業主(会社)が健康保険料の半額を負担することが一般的なので、退職後の健康保険料は在職中に給与から差し引かれていた額の約2倍になります。
国民健康保険に加入する
住んでいる市区町村国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に手続きをします。手続きには退職日の確認できる書類が必要ですので、担当窓口に必要書類を事前に確認しましょう。
国民健康保険料の算出方法は市区町村ごとに基準が異なりますが、一般的には前年の収入や資産などをもとに計算されます。また、国民健康保険には扶養家族はないため、配偶者や子どもなどの在職中に被扶養者だった人も健康保険料を負担することになります。
ただし、会社都合での退職の場合には、国民健康保険料の軽減措置を受けられることがあります。解雇や雇い止めなどで退職することになった人は、この制度の対象になるかもしれません。
家族や配偶者の扶養に入る
健康保険に加入している家族(被保険者)の被扶養者になる方法もあります。扶養に入るには条件があります。
・60歳未満の場合、将来の年収の見込みが130万円以下
・被保険者と同居している場合は、将来の年収の見込みが被保険者の年収の半分より少ない
・被保険者と別居の場合は、将来の年収見込みが被保険者からの仕送り額より少ない
※ただし、失業給付を受給している場合は日額によっては扶養に入ることはできません。
被扶養者として認められると、新たに健康保険料を追加で支払う必要はありません。そのため、費用の面では負担が少ないです。上記の条件に当てはまっていたら、扶養する被保険者の健康保険事務局に扶養に入ることができないか問い合わせてみると良いかもしれません。
退職日によって変わる社会保険料
月末に退職した場合の社会保険料
社会保険では退職日の翌日が資格喪失日です。資格喪失日を含む月は、健康保険料がかかりません。
つまり、月末に退職した場合は資格喪失日が翌月1日なので、退職月の健康保険料がかかります。例えば、退職日が8/31だと資格喪失日は9/1になり8月分は健康保険料が発生しますが、9月分はかかりません。
月の途中で退職した場合の社会保険料
退職日が月の途中であれば、退職月の健康保険料はかかりません。例えば、退職日が8/20だと資格喪失日は8/21のため、資格喪失日を含む8月分の健康保険料は発生しません。つまり、月の途中で退職した場合の健康保険料は前月分までとなります。
会社によっては前月分の健康保険料を今月分の給与から控除していることが多いので、退職時の給与からも健康保険料が差し引かれていることがあります。保険料に不明点がある場合は、差し引かれている健康保険料がいつの分なのかを会社に確認してみることも大切です。
しかし、資格取得日(一般的には入社日)と資格喪失日が同じ月の場合は、この月の健康保険料は発生します。これは「同月得喪」といって、意図的に入社と退職を繰り返すことで資格喪失による健康保険料の支払い回避を防ぐための仕組みです。
保険料の計算は資格喪失日に注意
資格喪失日とは健康保険証が使えなくなる日のことですが、資格喪失日が健康保険料の計算の基準になります。退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日を含む月から健康保険料を支払う必要がありません。退職日=資格喪失日でないのは、退職日が資格喪失日だと在職中にも関わらず退職日に健康保険証が使えなくなり、保険としての役割に矛盾が生じるからです。
社会保険料は日割り計算しない
健康保険料は日割り計算されないため、退職月の分の健康保険料が発生するかどうかは退職日によって変わります。そのため、月末で退職すると月の途中で退職する場合に比べて1カ月分多く健康保険料が給与から差し引かれます。
月末で退職することが損というわけではありません。退職後に任意継続や国民健康保険に加入する場合は、資格取得日を含む月の分の健康保険料を支払う必要があるからです。
例えば、退職日が8/20だと給与から差し引かれる健康保険料は7月分までですが、新たに加入する健康保険では資格取得日が8/21なので8月分の健康保険料が発生します。退職日が8/31だと給与から8月分の健康保険料が差し引かれ、9/1から新たに加入する健康保険では9月分から支払えば良いことになります。
退職後の社会保険に関する手続き
被保険者資格喪失証明書を提出先へ
退職後に国民健康保険に加入もしくは家族の被扶養者となるときは、一般的に被保険者資格喪失証明書の提出が必要です。被保険者資格喪失証明書の発行は、加入していた健康保険の事務局(全国健康保険協会であれば年金事務所)に依頼します。
年金事務所は窓口、郵送どちらでも手続きはできますが、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険の加入手続きをする必要があります。保険組合によっては取り扱いが異なることがあるので、健康保険組合事務局に問い合わせてみましょう。
扶養に入る場合は被扶養者届を郵送
退職後に家族の被扶養者となる場合は、被保険者である家族の加入している健康保険の事務局へ被扶養者(異動)届を提出します。ただし、被扶養者(異動)届は個人が直接事務局へ提出するのではなく、会社を通じて行う手続きなので被保険者の勤務先に被扶養者を追加したい旨を伝えましょう。被扶養者の認定には、収入や続柄を確認するための書類の提出が必要になることがあります。
任意継続の場合は必要書類を健保組合へ
任意継続する場合は、在職中に加入していた健康保険の事務局へ手続きをします。「任意継続被保険者資格取得申出書」と、被扶養者がいる場合は収入確認の書類などの提出が必要です。
全国健康保険協会に加入していた人は住んでいる全国健康保険協会支部、健康保険組合に加入していた人は健康保険組合の事務局が受付窓口です。いずれの場合でも、退職日の翌日から20日以内が提出期限ですので注意してください。
まとめ
国民健康保険は市区町村の窓口、任意継続は加入している健康保険の事務局にそれぞれ問い合わせれば、本人確認のうえ退職後の健康保険料を知ることができます。どちらが安くなるかは個人の状況によって異なるうえに、それぞれ手続きの期限がありますので、退職前に健康保険の選択肢を知っておくことは大切です。