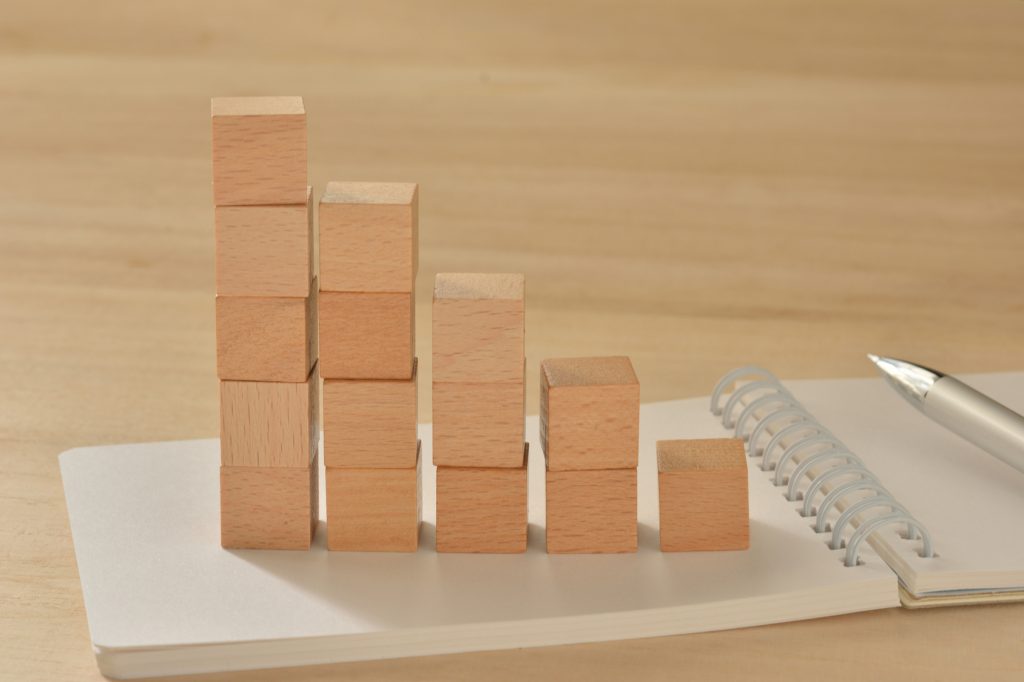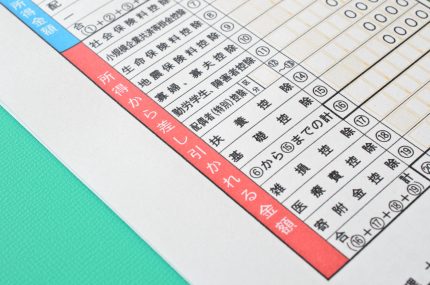遺族共済年金は遺族年金の一種であり、共済組合に加入している人に万一のことがあった際に受給することができます。しかし、受給するためにはいくつかの手続きが必要です。今回はその手続きの方法と、受給できる目安金額の試算方法を紹介します。
目次
遺族年金の種類と受給資格
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金や厚生年金、または共済組合に加入している人が亡くなった際に、遺族に支給される年金です。国民年金加入者には遺族基礎年金のみが、厚生年金や共済組合加入者には遺族基礎年金に上乗せする形で遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。また、受給するためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
遺族厚生年金との違い
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者に万一のことがあった際にその遺族に支給されるもので、厚生年金には会社員などが加入します。遺族年金と違いがあるというよりも、「遺族厚生年金は遺族年金の一種である」ということができます。ただし、遺族年金と遺族共済年期には違いがあり、遺族共済年金は公務員などの共済組合員の遺族に受給資格が発生します。
受給できる遺族の範囲と受給順位
遺族共済年金の遺族の受給範囲は、受給順位が上から順番に、配偶者と子、両親、孫、祖父母と定められています。それぞれに条件があり、子や孫には「18歳に到達した日以降最初の年度末までの間にあって配偶者を持たない人」もしくは「組合員が亡くなった時点から引き続き障害等級1級または2級の障害を持っている人」が該当します。
夫や両親、祖父母の場合は60歳から支給が開始されます。いずれの受給該当者であっても、組合員の収入で生計を維持していた人に限ります。なお、「生計を維持していた人」というのは、年収が8,500,000円未満、もしくは所得額換算で6,555,000円未満の人を指します。
受給資格と発生要件
受給資格は前述の条件を満たしている人に限ります。遺族年金の発生には以下の4点があり、いずれか1つに該当する必要があります。
1. 共済組合員が亡くなった場合
2. 組合員期間中に病気や怪我によって初診を受け、その日から5年以内かつ退職後に亡くなった場合
3. 障害共済年金の障害等級が1級または2級に該当する人、もしくは障害年金の障害等級が1級〜3級に該当する人が死亡した場合
4. 組合加入期間が25年以上に至る人、もしくは退職共済年金などの受給権を持つ人が亡くなった場合
遺族共済年の金額は?
遺族共済年金の計算方法
遺族共済年金の年金額は、次の計算式によって算出します。
年金額=厚生年金給付額相当額 + 職域年金相当部分 +(中高齢寡婦加算)
金額の算出方法は短期要件か長期要件かで変化します。短期要件とは前述発生要件の1~3に該当する場合、長期要件は4に該当する場合に当たります。
短期要件と長期要件の場合
まず厚生年金相当部分の計算は、
標準報酬月額 × 給付乗率/1,000 × 組合加入期間月数 × 3/4
により算出します。給付乗率は、平成15年の3月31日の組合加入期間に関しては7.125を、それ以降に関しては5.481を使用します。
次に職域年金相当部分も同様の計算式によって算出しますが、給付乗率については次のようになります。
■長期要件でかつ組合加入期間が20年未満である場合
・平成15年の3月31日の組合加入…0.713
・それ以降の加入…0.548
■短期要件の場合(組合加入期間が300月を下回る場合は300月として算出)
・平成15年の3月31日の組合加入…1.425
受給額の目安となる早見表(単位:円)
| 平均標準報酬月額 | 遺族厚生年金年額 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金年額 (配偶者と子1人) | 遺族基礎年金+遺族厚生年金年額 (配偶者と子2人) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 295,965 | 1,300,565 | 1,599,865 |
| 250,000 | 369,956 | 1,374,556 | 1,673,856 |
| 300,000 | 443,948 | 1,448,548 | 1,747,848 |
| 350,000 | 517,939 | 1,522,539 | 1,821,839 |
| 400,000 | 591,930 | 1,596,530 | 1,895,830 |
| 450,000 | 665,921 | 1,670,521 | 1,969,821 |
| 500,000 | 739,913 | 1,744,513 | 2,043,813 |
| 550,000 | 813,904 | 1,818,504 | 2,117,804 |
| 600,000 | 887,895 | 1,892,495 | 2,191,795 |
| 620,000 | 917,492 | 1,922,092 | 2,221,392 |
※受給対象者が配偶者のみの場合、遺族厚生年金と同一の金額となります。
遺族年金の支給停止について
夫、父母、祖父母の支給停止条件
夫、父母、祖父母への遺族年金の支給は60歳以降に開始されるため、60歳に至るまで支給停止状態が続きます。ただし、障害共済年金で障害等級が1級もしくは2級、障害年金で障害等級が1級〜3級と認定されている場合には支給されます。これは、60歳以降もしくはある水準以上の障害状態である場合には稼得能力が低下すると判断されるためです。
妻と子供の支給停止条件
厚生年金や共済加入者が亡くなった時点で遺族年金の支給対象に妻と子がいる場合は、子に対する遺族年金の支給は停止され、代わりに妻が受給します。ここでの子とは「18歳に到達した日以降最初の年度末までの間にあって配偶者を持たない人」を指し、支給要件を満たす子がいない場合もしくは子が結婚した場合などには、妻への遺族年金の支給が停止されます。
夫と子供の支給停止条件
厚生年金や共済加入者が亡くなった時、支給対象に妻と子がいる場合は、夫に対する遺族年金の支給は停止され、代わりに子が受給します。ただし、平成26年の4月以降に発生した遺族年金で、夫が遺族基礎年金の受給権を所有している場合には、子の代わりに夫が受給します。
公務遺族年金について
公務遺族年金の受給要件
公務遺族年金の受給要件には以下の3つがあります。
1. 共済組合加入者が公務、つまり仕事によって病気や怪我など(公務傷病)をし、それが原因で亡くなった場合
2. 共済組合加入者が加入期間中に初診を受けた公務傷病によって、初診を受けた日から2~5年で亡くなった場合
3. 公務障害年金で障害等級1級または2級と認定されているものが、障害の発生の原因である公務傷病で亡くなった場合
公務遺族年金の給付額
給付額は以下の式によって算出します。
公務遺族年金 = {(公務遺族年金算定基礎額)/(死亡日の年齢区分に応じた終身年金現価率)} × 調整率
ただし算出した金額が以下の式の金額よりも低い場合は、次の式の金額が支給されます。
1,038,100円 × (各年度における国民年金法の改定率) - (厚生年金相当額)
公務遺族年金算定基礎額は、組合員期間が300月未満の場合は
(給付算定基礎額)× 2.25 /(組合員期間月数)× 300
30月以上の場合は
(給付算定基礎額)× 2.25
によって算出します。
公務遺族年金の支給停止の条件
公務遺族年金の支給は、以下の3つの条件に該当した場合に停止されます。
1. 夫、父母、祖父母が受給者の場合、60歳に至るまでの期間
2. 配偶者に受給資格がある場合の子
3. 遺族基礎年金の受給資格の所有者が子である間、配偶者が受給資格を有していない場合
遺族共済年金の受給権消滅について
受給権の消滅要件
公務遺族年金の受給権は、以下の8つの条件に該当した場合に消滅します。
1. 亡くなった場合
2. 婚姻した場合
3. 直系の血縁関係にある、もしくは直系姻戚以外の人に養子に入る場合
4. 亡くなった共済加入者との親族関係が終了した場合
5. 30歳未満で公務遺族年金の受給権を得た妻が、その受給権の理由と同じ理由で遺族基礎年金の受給権を得ずに、5年が経過した場合
6. 5の遺族基礎年金と公務遺族年金の受給権の取得が逆の場合
7. 障害等級条件に該当しない子や孫が、18歳に到達した年度末に至った場合
8. 障害等級の条件に該当したする子や孫が、18歳年度末から20歳に至るまでの間に障害の程度が軽くなった場合、もしくは障害を持ったまま20歳に到達した場合
子供のいない30歳未満の妻の場合
組合加入者であった夫が亡くなって、30歳未満で遺族共済年金の受給権を得た妻は、以下の条件を満たす場合に期限付きの給付となります。
1. 上記の条件を満たしていて、かつ子供がいない場合
2. 上記の条件を満たしていて、かつ子供がいて遺族基礎年金の受給権を得ている場合
1の場合には5年の期限付きで支給されます。2の場合には、妻が30歳に至るまでに遺族基礎年金の受給資格を失った時から5年が経過するまで支給されます。なお、ここでの子とは「障害等級条件に該当する子」を示します。
まとめ
遺族共済年金を受給するためには、子供の障害等級や受給者の年齢など細かな条件を満たしている必要があります。万一の際に遺族年金受給のための手続きを迅速に進められるように、受給要件と受給金額をチェックしておきましょう。