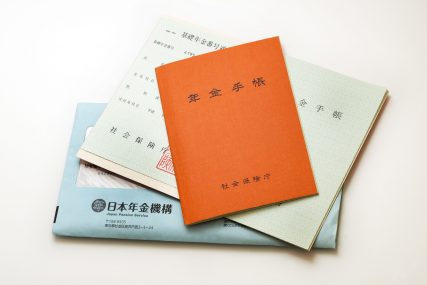「できる限りムダを省いて賢く貯金したい」とは、多くの人が考えていることではないでしょうか?目標があればお金を貯めるために我慢するのも苦にならないかもしれません。一口に貯金と言っても、方法や考え方は様々です。この記事では、効率的にお金を貯めるための方法について紹介します。
目次
無理のない貯金額を設定する
貯金は収入の10~30%が目安
貯金をする場合、毎月の給与額や収入額から貯金する割合を決めていくという方法があります。一般的に、月の収入の10~30%程度を貯金額の目安にすると、無理のないペースでお金を貯められるとされています。現状を考慮して、目安よりも貯金割合を増やすことも可能です。
例えば、賃貸住宅住まいの人よりも、社宅や寮に住んでいる人の方が月々の固定費は抑えられると言えます。また、実家住まいの人は、住宅費だけでなく食費や光熱費もあまりかからないことが多く、その分貯金へ回しやすい傾向にあります。共働き夫婦の場合、一方の収入をそのまま貯金に回すことができる場合もあります。
先取り貯金をする
給料の一部を別口座に移す
効率的に貯金をしていくには「先取り貯金をする」という手段もあります。「1月の収入から生活費を差し引いて残ったお金を貯金に回す」という考え方ではなく、例えば「1か月に〇〇円貯金をする」と決めておき、給料が振り込まれた時点でその金額を給与とは別の口座に移してしまうという方法です。別口座に移した後はそのお金はないものとし、残されたお金で生活をするように心がけると良いでしょう。
封筒でお金を4つに分ける
給料が振り込まれた後、現金を「生活費」「交際費等」「趣味に使う費用」「貯金」の4つに分けるという方法もあります。このようにしておけば、各費目で無駄遣いをすることも減り、「どこで余分な費用が発生しているのか」を発見しやすくなります。先取り貯金と同様に、「貯金に回すお金を最初から設定しておく」という点がポイントです。
財形貯蓄や自動積立定期預金を利用
勤務する会社によっては、財形貯蓄や自動積立定期預金が利用できることがあります。どちらについても、一度申請や登録をしておけば毎月決まった額のお金が貯金に回されることになるため、「自分は意志が弱い」と考えている人にとっては貯金をするのに有効な場合があります。なお、自動積立定期預金を利用する場合には、金利や付帯サービスの有無などを事前に確認しておきましょう。
小銭貯金は簡単な貯金の仕方
1日の終わりに財布の小銭は貯金箱へ
手軽な貯金方法として、「小銭貯金」を実施している人もいます。1日の終わりに財布の中身を点検し、余っている小銭はすべて貯金箱に入れてしまうという方法です。貯金箱を使う利点として、たまっていく様子が見た目や重さで確認できるためモチベーションアップに繋がりやすい、ということが挙げられます。
500円玉貯金をする
小銭貯金の一種ですが、500円玉貯金をするという方法もあります。毎日の終わりに財布の中身を見て、500円玉を見つけたら「即・貯金」という方法です。この貯金方法のメリットは、こつこつと積み上げていけば20万円、30万円規模の貯金も目指しやすいという点です。
貯金の目標を立てる
まずは100万円を目標
いきなり「1000万円貯める」などと大きな目標を立てても、途中で挫折してしまう可能性が高まります。「まずは100万円」など、頑張れば手の届きそうな金額に目標を設定し、それに向けてできることから始めていくのが良いでしょう。
次は200万円や300万円を目標にする
「手の届く目標」を達成したら、目標値を引き上げていきます。ここでも金額をいきなり引き上げたりせず、200万円・300万円などと無理のない範囲で目標を設定することが大切です。
最終的に1000万円を目指す
100万円単位などで目標をクリアしていくことができれば、1000万円貯金の達成も現実味を帯びてきます。「1000万円あれば〇〇をする」など、自分へのご褒美を用意しながらモチベーションアップにつなげていきましょう。1000万円あれば住宅購入時の頭金にできたり、欲しい車が買えたり、起業の資金にしたり、いろいろな使い道が考えられます。
増やすには積立投資を利用するべき?
低金利の定期預金ではお金は増えない
お金を「貯める」のではなく「増やす」ことを考えるならば、定期預金等を利用するという選択肢もあります。しかし、通常の普通預金口座に預けるよりはメリットが受けられる可能性も高いものの、金利の低い定期預金では満足のいく運用はできないかもしれません。
リスクを取って積立投資の利用も検討
ある程度のリスクが許容できるならば、NISAのような積立投資を利用することも可能です。積立投資では、毎月一定額を投資信託に投資すると運用益が生まれる可能性があります。NISAは比較的少額から投資することができ、配当は非課税対象となるため、資産を増やしたい人は利用を検討するのも良いでしょう。
まとめ
お金を貯める目的は人それぞれですが、モチベーションを維持しながら貯金を続けられる方法を取ると高額な目標も達成しやすくなります。また、「お金を増やす」という選択肢もありますが、この場合はリスクを取る可能性もあることを念頭に置き、自分に合った方法を検討する必要があると言えるでしょう。