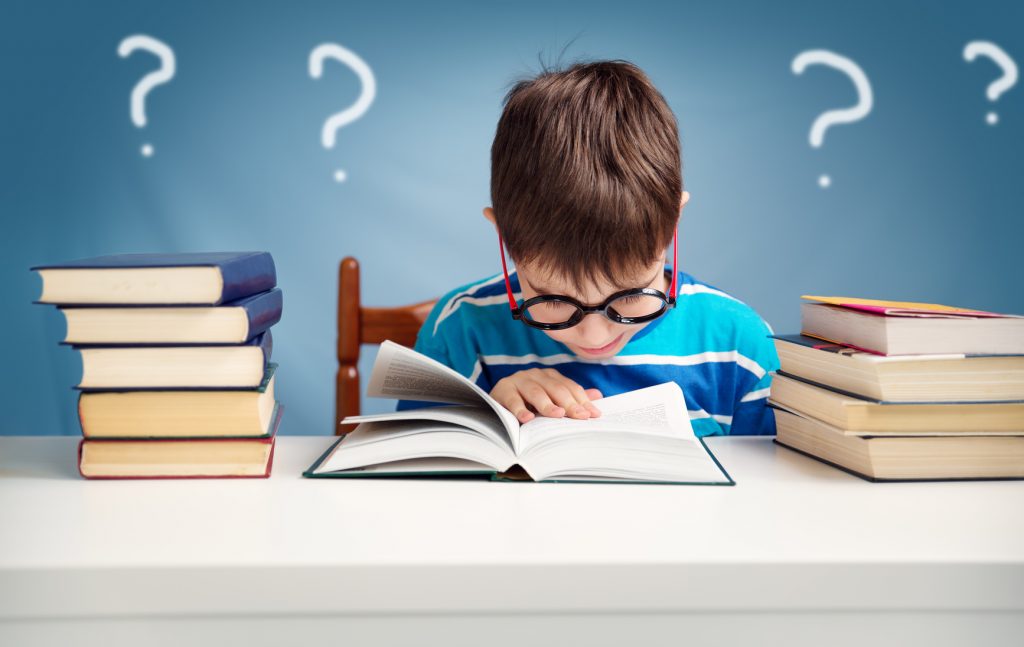「生命保険料控除証明書って何に使うの?」「何が書いてあるの?」といった疑問を抱いたことはありませんか?中には「控除証明書を提出しても大差がない」「面倒くさい」という理由から、そのまま捨ててしまった経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。今回は、生命保険料控除証明書の意味や利用方法について詳しく解説します。
目次
生命保険の控除証明書とは?
生命保険料控除とは、所得税と住民税を算出する対象となる所得から、その年の1月〜12月に払い込んだ保険料の一定額が控除される制度です。
生命保険料控除証明書は、生命保険に加入している人に対して保険会社が年間の払込保険料額を証明するもので、生命保険料控除制度を利用する際の添付資料と決められています。控除証明書には契約者名や適用制度(新制度・旧制度)、年間払込保険料の申告額など、控除制度の申告に必要な事項が記載されています。
控除証明書が自宅に届く時期は、払込方法や各生命保険会社の発送スケジュールによって異なります。おおまかな目安としては以下の通りです。
・毎月払い : 毎年10月中旬頃から順次発送
・年払い/半年払い : 10月中旬頃から順次発送
・一時払い : 10月中旬頃から順次発送(1回のみ)
・前納 : 契約月の翌月に証明書を送付
・団体扱い(給与天引き) : 契約者に送付なし(勤務先に一括して証明)
結婚などで姓が変わった場合、新たな姓を表示している証明書が必要になることがあります。また、転居で住所が変わっている場合は証明書が届かないこともありますので、契約時に登録した事項に変更が生じた際は、早めに各種手続きをしておいた方が安心です。なお、払込期間満了などによってその年に保険料が払われていない場合、証明書は発行されません。
万一紛失した場合は?
もし控除証明書を紛失した場合、再発行の手続きができます。契約担当の職員や保険会社のカスタマーセンターに電話で相談する方法の他、国内に存在する生命保険会社の約8割がインターネットでの再発行手続きに対応しています。日中は忙しくてカスタマーセンターに電話ができない人や、思い立った時に手続きを済ませておきたい人にとっては大変便利なシステムです。
再発行までの所要日数は約1週間としている会社が多いですが、年末調整や確定申告の時期は混み合う可能性があります。できるだけ余裕を持って手続きを済ませておくことをおすすめします。
また、インターネットでの再発行には、加入している契約の証券番号が必要です。「保険証券」や保険会社から送付される「契約内容のお知らせ」などを手元にあらかじめ置いておくとスムーズな手続きを行えます。
控除証明書はいつ使う?
控除証明書は、年末調整や確定申告の添付資料として使用します。その年に解約・失効した契約についても証明書が届きますので、忘れずに申告しましょう。また、複数の生命保険に加入している場合は、契約の件数に応じて証明書が届きます。
申告書の「新保険料」「旧保険料」という表示の内訳については、証明書内の「適用制度」欄で確かめることができます。申告額の計算方法が分からない場合には、ホームページ上で計算ができるツールを準備している保険会社もあります。控除証明書に記載されている数字を入力するだけで控除額が算出できるため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
控除額の計算には、自分名義の契約の他、自分名義でない契約の保険料負担をしているものも含みます。例えば、妻名義の契約の保険料を夫が負担している場合、夫の生命保険料控除として申告することが可能です(保険料を負担している証明の提出が必要な場合があります)。
生命保険料控除は、「保険金受取人が保険料の支払いを行っている本人・その配偶者・その他の親族(個人年金は本人・その配偶者)である場合」を対象としています。契約者が誰であるかということよりも、受取人が誰であるかという点が重要になりますので、申告書の受取人記入欄はしっかりと確認した上で記入しましょう。
万一、何らかの理由で申告が年末調整に間に合わなかったら、確定申告(還付申告)を行うことが可能です。また、過去に生命保険料控除の申告漏れがあった場合、過去5年間分をさかのぼって申告することもできます。控除証明書の再発行が必要になった際には、加入している保険会社のカスタマーセンターや担当職員に相談しましょう。申告についての詳細は、所轄の税務署に相談すると分かりやすく説明してくれます。
控除証明書に記載されている事項の訂正を行うと、申告の添付書類として使用することができません。控除証明書の到着後に契約の見直しを行った場合などには記載された金額と払い込み金額の間に相違が発生することがあるため、保険会社の担当職員やカスタマーセンターへ確認が必要です。
まとめ
生命保険料控除を受けるために控除証明書は欠かせません。複数の会社に契約がある場合は、証明書も複数枚になります。到着してから使用するまでの間には「保管場所を決める」などの対策を取っておくとスムーズに手続きを進めることができます。紛失が申告漏れにつながることもありますので、保管方法には十分に気をつけましょう。