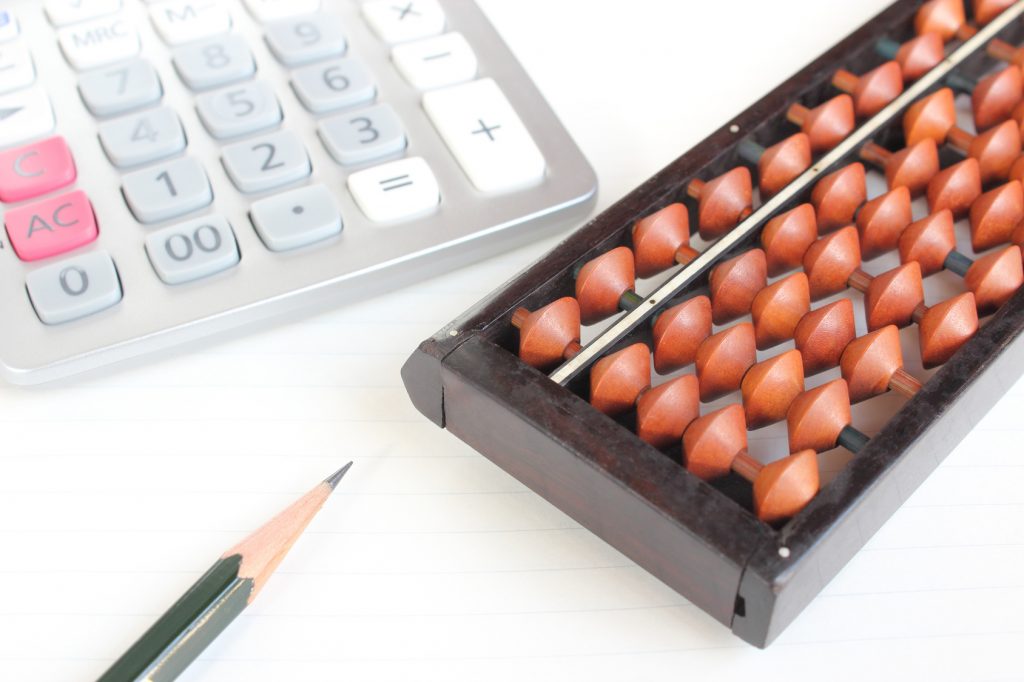個人年金保険の保険料支払いを行っている人は、所得税や住民税の控除が受けられます。今回は控除を受けるために必要な書類や、控除額の計算方法などを詳しく説明します。年末調整の申告書や確定申告書作成の予備知識としてだけでなく、実際に申告書を作成する際にも役立つ内容です。
目次
個人年金保険料控除を受ける要件
個人年金保険料控除(略:控除)は、契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているものが対象になります。特約の付加には4つの要件が設けられていて、そのうち1つでも満たしていない場合は特約を付加することができません。
個人年金保険料控除が受けられる保険契約の要件
1. 年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること
2. 年金受取人=被保険者であること
3. 保険料の払込期間が10年以上あること
4. 確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること(終身年金の場合は年齢要件なし)
また、税制適格特約を付加した場合は以下のような注意点があります。
・保険料の一時払いをした場合や、変額個人年金保険の保険料は対象外
・控除の要件を満たさない内容への変更不可(例:受取人を子供に変更など)
・特約のみの解約不可
・配当金がある場合や年金額を減額した際の返戻金がある場合、その金額は年金開始日まで積み立てられ、増額年金の買増に充当
・加入から10年以内は払済保険への変更不可
個人年金保険料控除の対象外の場合は?
控除の対象とならない「一般生命保険料」の対象になります。税制適格特約が付加されていない契約でも、生命保険料控除を受けることは可能です。
補足:所得税や住民税の控除は「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」という3つの項目に分けられています。平成23年以前の契約を旧制度、平成24年以後の契約を新制度とし「介護医療保険料」は新制度のみに含まれています。
個人年金保険料控除の上限や計算方法
平成23年12月31日までに締結した契約を旧制度、平成24年1月1日以後に締結した契約を新制度といいます。2つの制度は、控除額の計算方法や控除の適用上限額が相違しています。所得税と住民税を新・旧制度のそれぞれで計算する式は以下の通りです。
所得税の計算式
旧制度(平成23年以前の契約)
| 払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円(上限額) |
新制度(平成24年以後の契約)
| 払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 40,000円(上限額) |
住民税の計算式
旧制度(平成23年以前の契約)
| 払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円(上限額) |
新制度(平成24年以後の契約)
| 払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超 30,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
| 30,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円(上限額) |
旧制度・新制度両方の契約が保有し、それぞれが上限額に達している場合を例にとって解説します。
・個人年金保険 年間払込保険料 11万円(旧制度を適用)…所得税5万円、住民税3.5万円
・介護医療保険該当契約 保険料 10万円(新制度を適用)…所得税4万円、住民税2.8万円
・一般生命保険該当契約 保険料 5万円(旧制度を適用)+保険料 5万円(新制度)
…(旧)所得税3.75万円、住民税3万円 +(新)所得税3.25万円、住民税2.65万円=所得税7万円、住民税5.65万(上限超過のため、上限額の所得税4万円、住民税2.8万円)
旧制度のみ、新制度のみ、新・旧制度合わせた方法のいずれかで加入している契約について計算をし、控除額が一番大きくなるものを選びます。
※旧制度全体(一般生命保険料・個人年金保険料)の控除額上限は、所得税が10万円、住民税は7万円です。新制度全体(一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料)の控除額上限は、所得税が12万円、住民税は7万円です。
個人年金保険料控除を受ける方法
控除を受ける方法は、年末調整と確定申告の2種類です。生命保険会社が毎年10月頃から発送する「生命保険料控除証明書」は添付書類として必要であるため、大切に保管しておきましょう。
証明書には契約が新・旧どちらの制度に該当しているか、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料のどの控除に該当するかなどの、申告に必要な内容が記載されています。控除額の計算には「申告額」欄に記載の金額を使用します(「証明額」欄の金額は、証明書発行時点までに払い込まれている年内の保険料合計です。間違えないように気をつけましょう)。
サラリーマンは年末調整
会社に所属している人は、毎年11〜12月に「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を渡されます。申告書を記入する際は、手元に「控除証明書」があると便利です。「生命保険料控除」の枠内の該当欄に、年間払込保険料(証明書には申告額と記載)や控除額を記入し、控除証明書を添付して会社に提出します。
※受取人は正確に記入してください。場合によっては控除を受けられないことがあります。
※保険料が給与天引き(あらかじめ引かれている)の場合は、証明書の添付は必要ありません。
個人事業主や年末調整を受けていない人は確定申告
個人でビジネスを行っている人は、2月16日〜3月15日に行われる確定申告で控除の申告をします。控除を申告する際には、年末調整と同様、申告書の記載と「生命保険料控除証明証」の添付が必要です。
また、会社の年末調整に間に合わなかった人や、年金収入が400万以下の年金受給者に払込保険料がある場合、確定申告で控除の申告をすることによって所得税等の還付を受けられます(年金以外の所得が20万円以下に限る)。還付を受けるための申告は、過去5年にさかのぼって行うことが可能です。還付申告については、最寄りの税務署に尋ねると詳しく教えてもらえます。
まとめ
個人年金保険を節税につなげるための「要件」や「方法」についての理解は深まりましたか?現在、個人年金に加入している方や加入を検討されている方はもちろん、過去5年以内に加入していた方も覚えておいた方が良い情報と言えます。控除制度を有効に利用して、賢い資産形成に励みましょう!