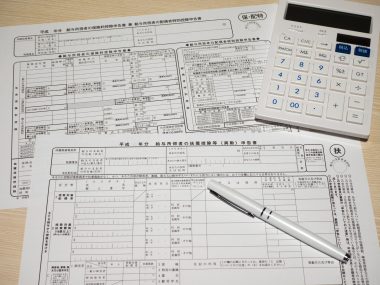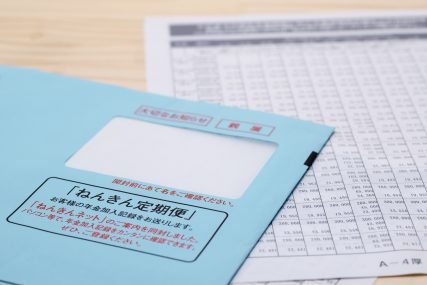老後の資金対策として注目されている確定拠出年金。この制度に加入している人は、所得税や住民税を節税することができます。また、その他にも税制上優遇されている部分があります。確定拠出年金への加入によってどの程度の節税が可能なのか、具体的なシミュレーションをしながら確認していきましょう。
目次
確定拠出年金の所得控除の種類は?
所得税額の計算をするにあたり、その年の支出金額や損失について控除の申告をすることが認められています。所得控除は「最低生活の維持」や「社会政策上の配慮」など、合わせて14種類に分類されています。
確定拠出年金は「小規模企業共済掛金等控除」の対象
「小規模企業共済」は、個人で事業を行っている人や小規模な法人の役員などが事業の廃業や退職時の備えとして加入する共済制度です。加入者が掛金を出し合う確定拠出年金は「小規模企業共済」と性質が似ているため、同じ枠内で所得控除の申告をします。
対象となる掛金は?
個人で支払いを行っている掛金は、その全額が控除の対象となります。個人型確定拠出年金に加入している人や、企業型確定拠出年金の加入者のうちマッチング拠出(企業の掛金に上乗せして個人で掛金を支払うこと)を行っている人は、その掛金全額を「小規模企業共済掛金等控除」として申告しましょう。
確定拠出年金による所得税や住民税の節税シミュレーション
所得税は年間の収入から必要経費(控除額)を差し引いた残額に税率を乗じて算出します。そのため、必要経費(控除額)が大きくなれば、納める税金は少なくなる仕組みになっています。
では、確定拠出年金に未加入の場合と加入している場合を比べると税額の差はどのくらいになるのでしょうか。「年収400万円の会社員」のケースでシミュレーションしてみましょう。
課税所得の計算方法と税率
所得税の計算を行うには、まず課税所得の算出が必要です。課税所得は「年間給与額 – 給与所得 – 給与所得控除」で求めることができます(千円未満の端数は切り捨て)。
給与所得控除額は下の表を使って算出できますが、年収が660万円未満の場合は「所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)」を用いて給与所得を求めます。
給与所得控除額(平成29年分)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 65万円未満 | 65万円 |
| 180万円以下 | 収入金額 × 40% |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30%+ 18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20%+ 54万円 |
| 660万円超 1,000万円以下 | 660万円超 1,000万円以下 |
| 1,000万円超 | 220万円(上限) |
参考 : 平成29年分給与所得控除額
課税所得に対し所得税率を乗じたものが「所得税」です。以下の表の通り、税率は収入によって段階的に上がるように定められています。
所得税速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考 : 所得税の速算表
では実際に「年収400万円・会社員・独身・確定拠出年金未加入・所得控除は基礎控除のみ」のケースで、所得税を算出してみましょう。
<課税所得を求める計算式>
400万円(年間給与額) − 134万円(給与所得控除) – 38万円(基礎控除) = 228万円(課税所得)
※「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の400万円の欄について、給与所得控除後の金額を利用した場合は「266万円 – 38万円(基礎控除) = 228万円(課税所得)」となります。
<所得税を求める計算式>
228万円(課税所得) × 10% – 9万7500円(控除額) = 13万500円(所得税額)
確定拠出年金による所得税と住民税の節税効果の計算例
【所得税】
先ほどと同じ条件の人が確定拠出年金に加入した場合の所得税を計算してみましょう。
「年収400万円・会社員・独身・基礎控除のみ」に「確定拠出年金加入(年間掛金18万円)」を加えたケース
<課税所得を求める計算式>
400万円(年間の給与額) − 134万円(給与所得控除) – 38万円 +(基礎控除) – 18万円(確定拠出年金の年間掛金) = 210万円(課税所得)
<所得税を求める計算式>
210万円(課税所得) × 10% – 9万7500円(控除額) =11万2500円(所得税額)
確定拠出年金未加入時の所得税額が13万500円だったのに対し、加入後の所得税額は11万2500円で、差額は1万8000円です。
【住民税】
住民税(所得割)は、課税所得に対して一律10%の税率を乗じて算出します。確定拠出年金未加入・加入それぞれのケースで計算してみましょう。(均等割の分は省く)
「確定拠出年金未加入のケース」
228万円(課税所得) × 10% = 22万8千円
「確定拠出年金に加入しているケース」
210万円(課税所得) × 10% = 21万円
確定拠出年金加入者は、住民税が1万8千円分軽減されることが分かりました。
確定拠出年金は掛金以外にも税制優遇制度がある
所得税や住民税が軽減されるほかにも、確定拠出年金には税制上優遇されている制度があります。
運用益が非課税
確定拠出年金の大きな特徴は、自分が選んだ投資先で資金を運用することです。もし運用実績が好調である場合、自分の資金が「儲け」となって返ってくる可能性があります。この儲けのことを「運用益」といいます。
定期預金や投資信託などの金融商品では利息に対して約20%の税金がかかりますが、確定拠出年金で得た運用益はすべて非課税扱いとなります。
受取時は一時金も年金も一定額まで非課税
60歳以降になると、今まで積み立てた資金を受け取ることが可能です。受取方法は「一時金」と「年金形式」の2種類があります。
一時金形式で受け取る場合は「退職所得」という種類に該当します。退職所得にも控除が認められており、勤続年数が20年以下の人は「勤続年数 × 40万円(80万円に満たない場合は80万円)」、20年を超える人は「800万円 + 70万 × (勤続年数 – 20年)」に該当する金額の控除が可能です。退職所得には会社からの退職金なども含まれます。退職にかかる所得が退職所得控除を越えた分に対して課税される仕組みになっています。
一方、年金形式で受け取るタイプの場合、65歳未満の人は公的年金と合算して70万円まで、65歳以上の人は120万円までが非課税となっています。
まとめ
確定拠出年金にはいくつかの税制優遇があります。実際に計算をしてみて、差額の大きさに驚いた人もいるのではないでしょうか。加入を検討する際には運用リスクだけに着目するのではなく、今回紹介したような税制優遇についても考慮に入れておくと良いかもしれません。