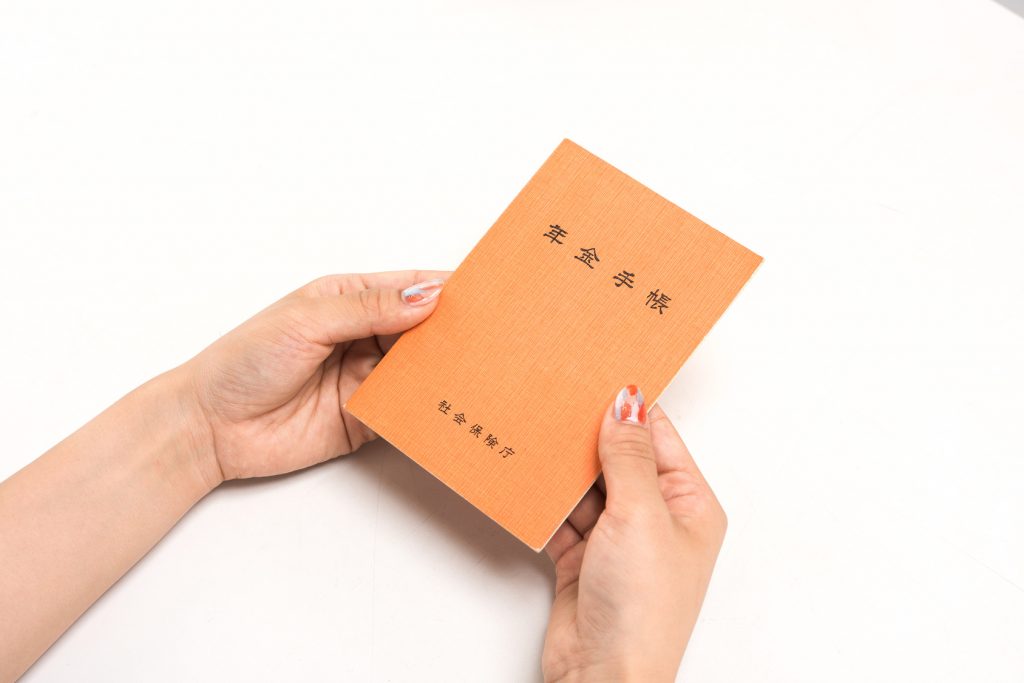国民年金では全ての国民が老齢・障害・死亡に対して給付金を受け取ることができますが、保険料の支払いは被保険者の種類によって異なります。この記事では、国民年金の第3号被保険者について紹介します。該当する要件や保険料の支払い方法などを確認してみてください。
目次
国民年金の被保険者の種類とは?
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人とその配偶者などが国民年金の第1号被保険者です。農業・漁業従事者も含まれます。保険料は自分で手続きを行い納めなければなりません。
保険料は、口座振替や納付書による支払い、クレジットカードでの支払いができます。あらかじめまとめて保険料を支払う「前納」をすると保険料が割り引かれることもあるので、資金に余裕のある人は市区町村の窓口で確認してください。また保険料の支払いが経済的に難しいときには、保険料免除や納付猶予(学生の場合は学生納付特例制度)を受けることができます。利用を検討しているのであれば、市区町村の窓口に相談するとよいでしょう。
第2号被保険者
国民年金加入者のうち、厚生年金(会社員)や共済組合(公務員)に加入している人を、第2号被保険者といいます。保険料は被保険者と事業主とで折半され、給与や賞与から天引きされて支払われます。天引きされた保険料の中には国民年金への拠出金も含まれるため、自分で国民年金の保険料の支払いをする必要はありません。
ちなみに65歳以上の厚生年金加入者や共済組合加入者で、老齢基礎年金や厚生年金などの受給権を得ている人は第2号被保険者とはなりません。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が、第3号被保険者です。第3号被保険者である人は、配偶者が加入する厚生年金もしくは共済組合が保険料を一括して負担してくれます。そのため、個別に保険料を納付する必要はありません。第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務する勤め先(事業主)へ届けを出して手続きを行ってください。
第3号被保険者になる要件とは?
配偶者が厚生年金に加入している
第3号被保険者になるための要件の1つ目は、配偶者が厚生年金や共済組合へ加入していることです。そのため、自営業者などの配偶者は第3号被保険者となることはできません。
第3号被保険者になる際は、配偶者の所属する事業主に「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出します。その後事業主から年金事務所へ届け出が行われ、手続きが完了します。年金事務所から郵送される該当通知書で、手続きの完了を確認してください。
年収が一定以下である
配偶者が厚生年金や共済組合の加入者であったとしても、本人に一定以上の収入がある場合には第3号被保険者となることはできません。配偶者の扶養に入るためには、年収が130万円未満(障害者や60歳以上の人の場合180万円未満)である必要があります。また上記に加え、扶養者と同一世帯の場合は年収が扶養者の年収額の半分未満であること、別居の場合は年収が扶養者からの仕送り額未満であることが要件とされています。
ここでいう年収とは、「年間の見込み収入額」です。そのため、給与所得等の収入がある場合は月額108,333円(130万円÷12カ月)、雇用保険等の受給者である場合は日額3,611円(130万円÷360日)を超えた時点で、扶養から外れることとなります。雇用保険のほか、公的年金や健康保険の傷病手当金、出産手当金なども収入とみなされます。
第3号被保険者のメリットとは?
保険料を支払ったことになる
第3号被保険者の国民年金保険料は、扶養者の給与から天引きで支払われています。ポイントは、「扶養者の支払う年金額は、第3号被保険者がいてもいなくても同額である」という点です。
つまり、制度としては「第3号被保険者の保険料は扶養者が支払う」という形がとられていますが、実質的には「第3号被保険者の保険料は扶養者が支払ったことになっている」と言えるかもしれません。しかし、老後の年金が減額されることなどはなく、保険料を支払ったものとして計算・支給されます。
離婚の際に3号分割が利用できる
3号分割制度とは、平成20年5月1日以降に第3号被保険者と扶養者が離婚をし、第3号被保険者からの請求があった場合、平成20年4月以降の扶養者の厚生年金記録を50%ずつに分割することができる制度です。
3号分割制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・平成20年4月以降に、婚姻中の第3号被保険者としての厚生年金記録があること
・原則として離婚などをした日の翌日から2年以内に請求があること
第3号被保険者の注意点とは?
年金額が少ない
国民年金保険料の納付が義務付けられている20歳から60歳までのうち全期間の保険料を納めた人は、老齢基礎年金を満額受け取ることができます。これは、第3号被保険者であっても同じです。満額の老齢基礎年金額は、773,300円となっています(平成20年4月分以降)。この金額を12カ月で割るとひと月当たりの年金額は64,441円程度であり、ひと月の収入として多いとは言えない金額であることがわかります。
国民年金基金など上乗せ給付の対象外
老齢基礎年金だけでは不安があるという人には、上乗せ給付ができる制度があります。例えば、第1号被保険者を対象とした国民年金基金や付加年金などです。厚生年金や共済組合に加入している人へは、厚生年金や共済年金が老齢基礎年金に上乗せして給付されます。
第3号被保険者には2016年12月までは上記のような上乗せ受給ができるような制度はありませんでしたが、2017年1月からは個人型確定拠出年金(i Deco)を利用できるようになりました。i Decoは「お金を運用しながら積み立てをし、原則として60歳になったら受け取る」という仕組みで、運用は定期預金か投資信託で行います。
掛け金が全額所得控除となったり、運用益が非課税となったりするなど、税金面で優遇されている点が特徴です。i Decoは、インターネット銀行や都市銀行などで取り扱っており、金融機関によって手数料やサービスに違いがあります。興味のある人は窓口に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
年齢制限がある
第3号被保険者には、一定の年齢制限があります。1つ目は第3号被保険者本人の年齢が20歳以上60歳未満であることです。2つ目は、扶養者の年齢が65歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていないことです。上記2点の制限から外れたときには、第3号被保険者の資格を喪失します。居住する市区町村の窓口か年金事務所で第1号被保険者への変更手続きを行わなければなりません。
第3号被保険者になる手続き方法
前述のとおり、第3号被保険者となるには配偶者の勤務先(事業所)に届け出を行うことで手続きが完了するため、自分自身で手続きをする必要はありません。ただし、第3号被保険者となる前に第1号被保険者としての保険料を口座振替で支払っていた場合には、銀行または郵便局で口座振替停止の手続きをしなければなりません。
口座振替停止の手続きには時間を要することがあるため、手続きタイミングによっては保険料の二重払いが起きてしまうことも考えられます。万が一「第3号被保険者となった後も第1号被保険者としての保険料が口座から支払われてしまった」という場合には、後に返金を受けることができるため、最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
まとめ
保険料の支払いなどで優遇されている第3号被保険者ですが、年齢・年収などいくつかの要件があります。要件の確認漏れなどが発生して第3号被保険者と認められなかった場合には、その間の保険料が未納扱いになってしまう可能性もあります。詳細まできちんとチェックした上で手続きを行うようにしてください。