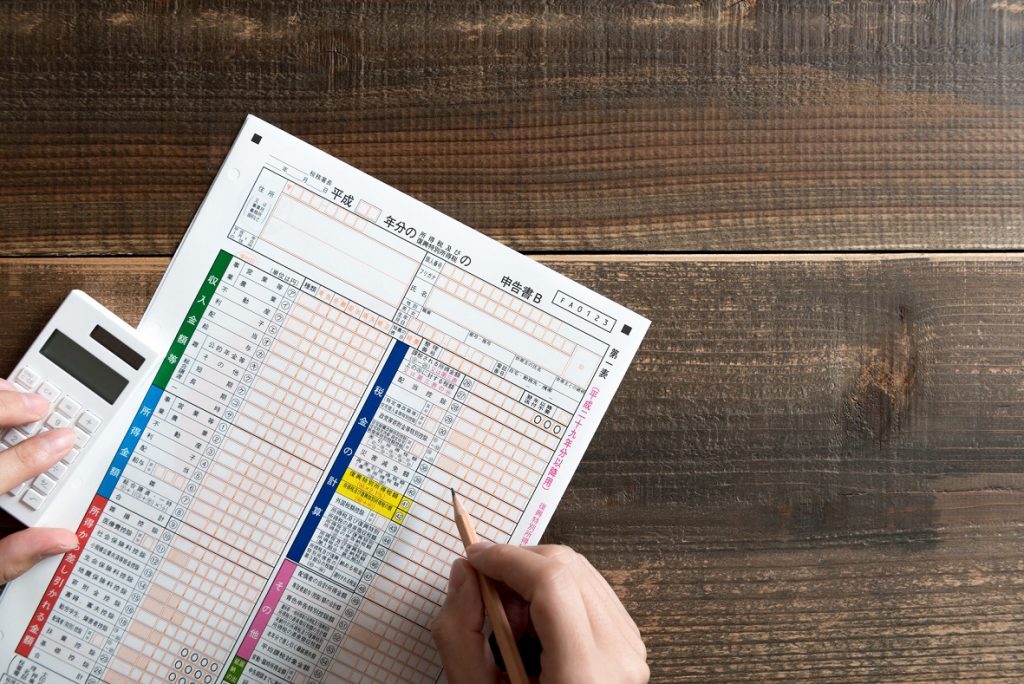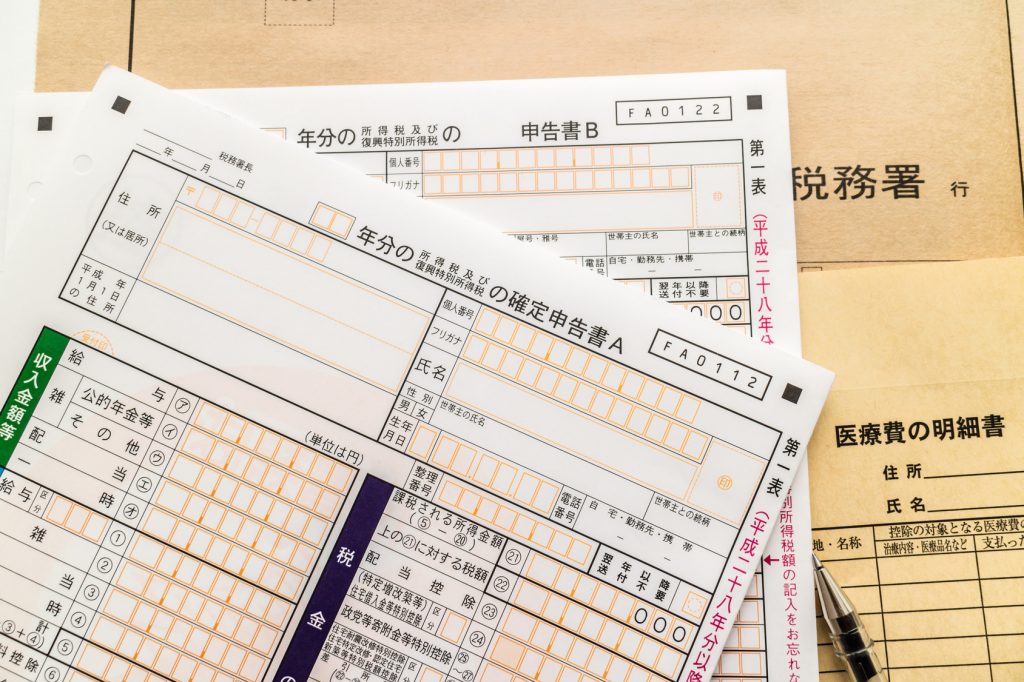一定以上の財産を保有している人が亡くなり、家族や子供にその財産を引き継ぐ際に発生する税金のことを「相続税」と言います。あまりなじみのない人も多いかもしれませんが、自分が相続に直面した時のために覚えておくとよいでしょう。この記事では、相続税に関するさまざまな知識を紹介します。
目次
相続税を計算する前に
土地・預金などの相続財産を計算する
相続税を計算する前に、まずは相続財産を確認しておくことが必要となります。「相続財産」と言うと、土地・建物・預金などの財産と思われがちですが、各種借り入れ・負債などの「マイナスの財産」も含まれることに注意が必要です。総資産からマイナスの財産を差し引くことによって、正味の相続財産の金額が判明します。
相続税の基礎控除額を計算する
正味の相続財産額が判明したら、次は相続税の基礎控除額を計算します。相続財産があればすべての人に相続税が課税されるわけではなく、「3,000万円+(法定相続人の数)×600万円」という計算式によって基礎控除額が算出されます。基礎控除額に達しない相続財産に対しては、相続税が課税されないことになります。
課税遺産総額を計算する
「正味の相続財産額」と「基礎控除額」を算出したら、両者の差額である「課税遺産総額」を計算します。この「課税遺産総額」を基にして、実際に負担する相続税額が決定されることとなります。
相続税の総額を計算するには?
相続税のシミュレーション
被相続人(死亡した人)の妻と子が相続人である場合を想定して、実際にシミュレーションしてみましょう。妻と子の2人で合計5,000万円の財産を相続するものとします。
この場合の課税遺産総額は、
5,000万円×(3,000万円+600万円×2人)=800万円 と計算できます。
課税遺産総額を法定相続分(妻が2分の1・子が2分の1)で割り振ると、妻・子ともに400万円となります。【相続税の速算表(※後述します)】に記載されている税率をこの金額へ乗じると40万円となります(今回の場合は妻、子ともに税率10%で控除額0円)。
ただし、遺産分割協議等によって、法定相続分と実際の相続金額とに相違が生じる場合も多いため、実際に相続する金額に応じた税額が適用されます。今回のケースにおいて、妻が4,000万円、子が1,000万円を相続すると仮定すると、各々の相続税額は以下の通りとなります。
妻の相続税額
40万円×4,000万円÷5,000万円=32万円
※配偶者の税額軽減の制度が適用されるため、妻の税額は0円となります。
子の相続税額
40万円×1,000万÷5,000万円=8万円
相続税早見表
上述のシミュレーション中で相続税の計算に用いた【相続税の速算表】は国税庁のホームページで確認することができます。相続金額(法定相続分)に対する税率・控除額が記載されているため、参考にしてください。
税金が減免されるケース
相続対象が基礎控除額以下である場合
相続税には基礎控除額が設けられており、相続財産が一定以上の金額でなければ相続税は課税されません。例えば、法定相続人の数を3人とすると、基礎控除額は
3,000万円+3人×600万円=4,800万円 と求められます。
実際の相続財産がこの金額以下である場合、相続税の課税対象外となります。
生命保険金の非課税限度額とは
相続税の基礎控除額に対して、被相続人の死亡によって死亡保険金が支払われた場合には「生命保険金の非課税限度額」が設けられており、法定相続人1人あたり500万円が非課税となります。
配偶者控除が適用される場合
上述のように、相続人が配偶者である場合には配偶者控除が適用されるため、税額が一部もしくは全額免除となります。具体的には、「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」を比較し、どちらか高い金額に対する控除が適用されます。
相続税と贈与税、どう違う?
税率や意味合いの違い
相続税も贈与税も、課税対象額が大きくなるほど高い税率が課される「累進課税制度」が採用されています。贈与税の場合は基礎控除(年間110万円)後の課税対象額が3,000万円以上である場合、400万円の控除後に55%の税率が課されます。一方、相続税においては、基礎控除後の法定相続分に応じた課税対象額が6億円を超える場合に55%の税率が課されます。
このように、相続税と贈与税の税率を比較すると、贈与税の方が税金の負担額が多くなる傾向にあることがわかります。この点には、生前に財産を家族に分配してしまう「相続税逃れ」を防止するという意図があると考えられています。
贈与税はいくらからかかるのか
贈与税は、年間110万円の基礎控除分を除いた贈与額が課税対象となります。贈与金額が年間210万円であるとすると、基礎控除後の贈与額は100万円となり、10%の税額が適用されるため、贈与税額は10万円となります。贈与額ごとに適用される税率は異なるため、詳細は国税庁のホームページなどを確認してください。
改正前後の違いに注意
平成27年1月1日以降、贈与税の制度は一部改正が行われました。具体的には、20歳以上の者が親や祖父母などの直系尊属から財産を贈与された場合(特例税率)とそれ以外の場合(一般税率)で、課税価額・税率・控除額に変更が生じています。
また、相続時精算課税制度においても、贈与者(財産を贈与する人)の年齢が65歳から60歳まで引き下げられた他、受贈者(財産を受け取る人)の範囲が推定相続人の孫にまで拡大(改正前まで孫は範囲外)されるという改正が行われているため、注意が必要です。
相続税の申告方法って?
申告が必要な人と期限
「基礎控除額を差し引いた相続財産総額が0円以上になる場合」には、相続税の申告を行う必要があります。被相続人が死亡して10か月以内に申告がないと罰金などのペナルティが発生することもあるため、期限を守るよう心がけてください。
申告に必要な書類
国税庁が定める所定の申告書の他、「誰がどのような形で財産を相続したのか」という点を証明する書類(生命保険金に対する「生命保険金明細書」など)が必要となります。紛失した場合やどんな書類か不明である場合などは、弁護士や保険会社へ相談してみるとよいでしょう。
税理士に代行を頼むことも可能
国税庁が定める所定の申告書は種類・数ともに多く、内容も多岐にわたるため、税理士などの専門家へ申告の代行を依頼することも可能です。税理士報酬は発生しますが、自分で申告する手間を軽減られる点、税額控除等のアドバイスを受けることができる点などのメリットもあります。
まとめ
相続税の計算方法や、贈与税との違い・改正前後の注意点などについて紹介しました。「相続税について考えたことがなかった」という人も、ゆくゆくは相続に直面することになるかもしれません。そのような際に慌てず適切な対応が取れるよう、必要な知識を身につけておきましょう。