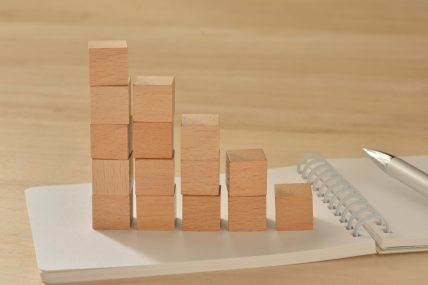生命保険のひとつである養老保険には、どのような特徴があるのでしょうか。養老保険は個人だけではなく、法人でも活用されています。養老保険とはどういった保険か、終身保険や個人年金保険との違いにも触れるとともに、満期保険金にかかる税金についても解説していきます。
目次
養老保険とは
養老保険は生命保険のひとつで、貯蓄性がある保険です。養老保険の特徴について、終身保険との違いについても触れていきます。
満期保険金と死亡保険金が同額
養老保険は保険期間が決められた有期の生命保険で、保険期間中に死亡、あるいは高度障害になった場合には、死亡保険金が支払われ、無事満期を迎えた場合は満期保険金が支払われます。満期保険金は死亡保険金と同額で、貯蓄性があります。
満期保険金は基本的には払込済み保険料を上回り、元本割れしません。ただし、医療保険や満期保険金を上回る高額な死亡保障などの特約がついているケースでは、元本割れすることがあります。
満期保険金は満期時に受け取らずに、据え置くことも可能です。据え置きをした場合には、保険会社が定める利率で利子がつきます。保険会社や商品によっては年金払いにも対応しています。
養老保険の保険期間は商品や加入年齢によって異なりますが、5年、10年といった短期から、30年、50年といった長期に及ぶものから選ぶことが可能です。養老保険を保険期間の途中で解約する場合には、解約返戻金が支払われます。ただし、解約返戻金は早期に解約するほど、払込済み保険料を大きく下回りますので注意が必要です。
支払いタイプは2種類
養老保険の支払い方法は、月払いや年払いなどの積立タイプと一回で支払う一時払いタイプがあります。支払う保険料の総額は、多い方から月払い、年払い、一時払いの順で、一時払いが利率の面では最も有利になります。
では、一時払いがお得かというと一概にはいえません。養老保険を一時払いにすると、死亡保障として加入する意味合いがほとんどなくなります。また、養老保険の保険料は生命保険料控除の対象ですが、一時払いの場合は保険料を支払った年しか所得から控除できないこともデメリットです。
終身保険との違い
養老保険と終身保険は死亡や高度障害に備えられ、必ず保険金が受け取れる貯蓄性のある保険で、中途解約した場合には解約返戻金が支払われるという点は同じです。一方で、養老保険には満期保険金がありますが、終身保険に保障が一生涯続くので「満期」がなく、満期保険金というものはありません。終身保険は存命中にお金を手にしたい場合は、高度障害の状態になった場合などを除いて、解約する必要があります。
保険料は保障内容が異なるため、一概に比較できませんが、養老保険の方が割高です。相続税対策や葬儀費用の準備で生命保険に入る場合には、終身保険の方が向いています。
個人年金保険との違い
個人年金保険は保険料払込期間終了後に、受取開始年齢から一定期間、あるいは一生涯、年金を受け取れる保険です。個人年金には、被保険者の生死に関わらず、一定期間年金が支払われる確定年金、被保険者が生きている場合に一定期間年金が支払われる有期年金、被保険者が生きている限り年金が一生涯支払われる終身年金があります。
養老保険と個人年金は貯蓄性のある保険という点では同じです。養老保険は保険期間の満了時に満期保険金が支払われるのに対して、個人年金保険は受給開始年齢から年金を受け取れるもので、年金の受取期間は種類によって異なります。
また、養老保険は死亡保険金と満期保険金が同額で、死亡保障を兼ねられます。一方、個人年金保険は死亡した時点までの払込済み保険料相当額が死亡保険金として支払われるため、死亡保障の機能がないことも異なる点です。
さらに、養老保険の保険料は所得税の生命保険料控除の対象なのに対して、個人年金保険は個人年金保険料控除の対象です。ただし、個人年金保険料控除を受けるためには、保険料の払込期間が10年以上、年金の受取開始年齢が60歳以上で受取期間が10年以上といった要件があります。
養老保険に加入する目的は?
貯蓄性があり、死亡保険金か満期保険金のいずれかが支払われる養老保険は、どういった目的で加入する保険なのでしょうか。
老後資金や学資保険代わりに
養老保険は無事、保険期間の満了を迎えられた場合は、元本割れせずに満期保険金を受け取れるため、死亡保障を兼ねながら貯蓄ができます。養老保険への加入目的として、老後の資金の確保のほかに、学資保険代わりに活用する方法が挙げられます。
養老保険と学資保険は積立方式で死亡保障の機能があり、満期に保険金が受け取れること、解約した場合には解約返戻金があることが共通点です。ただし、学資保険は加入時の子どもの年齢などに制限があります。予定利率などを比較して、有利な商品を選びましょう。
養老保険のメリットとは
養老保険にはどんなメリットがあるのか、特徴をもとにみていきましょう。
貯蓄と死亡保障を兼ねられる
養老保険は死亡保険金が満期保険金と同額で、必ずいずれかが受け取れ、掛け捨てではないため、死亡保障と貯蓄を兼ねられることがメリットです。昨今ではバブル期と異なり、養老保険の予定利率は低いですが、銀行にお金を預けていても定期預金の利子はわずかです。
養老保険の満期保険金は、基本的に払込済み保険料を上回ります。養老保険は実質的に無料で死亡保障の備えをしながら、まとまったお金を手に入れることができるのです。
計画的にお金を貯めやすい
養老保険は積立方式の保険で、月払いの場合、毎月保険料が口座から引き落とされますので、貯金が苦手な人でも、強制的に計画性を持って貯蓄ができることもメリットです。養老保険は保険期間と保険金額を選ぶことができますので、必要な時期にまとまったお金を用意しやすいです。
また、解約すると解約返戻金が戻ってきますが、早期の解約ほど不利になります。解約すると損をすることも、貯金が苦手な人も解約せずに満期を迎えやすい要因です。
養老保険のデメリットとは
一方で、養老保険にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。昨今では、養老保険はさほど有利とはいえない保険商品です。
保険料が割高
養老保険は積立方式で掛け捨てではないため、保険料が割高です。入院保障などの特約をつけることもできますが、保険料がさらにアップし、満期保険金が払込済み保険料の総額を下回ってしまうケースが多いです。
バブル期は資産運用目的で養老保険に加入するケースが多かったですが、予定利率が低い昨今では、有利な運用方法とは言い難いものがあります。割安な保険料で資産運用を図るのであれば、ハイリスクハイリターンではありますが、外貨建て養老保険を検討してみましょう。
保険を見直しにくい
養老保険は保険料が高いため、家族の状況が変化したときに、保険の見直しを検討することが想定されます。しかし、養老保険の解約返戻金は早期の解約であればあるほど、払込済み保険料を大きく下回ってしまい、損をすることになるため、保険の見直しがしにくいです。養老保険に入るときは、家計に無理のない保険料を設定することが大切です。
また、バブル期に契約した養老保険は予定利率が高い「お宝保険」といわれるもので、現在では同水準の養老保険に加入することはできません。「お宝保険」は、家計に無理のない範囲内で解約しないようにしましょう。
養老保険は法人も活用できる?
養老保険は法人が契約者として、役員や従業員を被保険者として加入する形態でも活用されています。法人は養老保険に福利厚生プランで加入することで、さまざまなメリットがあります。
法人は福利厚生目的の加入がおすすめ
法人は養老保険を活用する場合、福利厚生プランと呼ばれる契約形態がおすすめです。被保険者は従業員で、契約者は法人、死亡保険金の受取人は被保険者の遺族、満期保険金の受取人は法人とします。
万が一、従業員が在職中に亡くなった場合には、遺族は死亡退職金として死亡保険金を受け取ることができます。満期を迎えたときには法人が満期保険金を受け取ることができますので、退職金の原資に充てることが可能です。
ただし、死亡退職金の支払いを巡るトラブルにならないように、死亡保険金を死亡退職金に充てることを就業規則の福利厚生規定に明記しておくことが大切です。
保険料の損金算入などのメリットも
養老保険に福利厚生目的で加入することによるメリットとして、保険料の1/2を損金算入することが挙げられます。税負担を軽減しつつ、福利厚生制度を充実することで、従業員のモチベーションアップや採用面での効果が期待できます。また、退職金の支払い時期が重なると赤字に陥るリスクがありますが、満期保険金や解約返戻金を充てることでリスクの軽減が可能です。
また、退職金の原資の準備には、中小企業共済を利用する方法もありますが、懲戒解雇した従業員にも直接退職金が支払われる、一度納付した掛金は返還されないといったデメリットがあります。養老保険を退職金の原資とすれば、独自の福利厚生規定に則って、退職金を支給すするなど、柔軟に対応することが可能です。
さらに、万が一、経営不振に見舞われ、倒産のリスクがあるときには、養老保険を解約して経営資金に充てることもできます。
こちらの記事では基本的な養老保険の紹介から終身保険・個人年金との違いについて詳しく紹介しています。
満期保険金にかかる税金は?
養老保険の満期保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか。契約形態による違いや計算方法についてみていきます。
契約形態によって異なる
養老保険の満期保険金を受け取ると課税対象になりますが、かかってくる税金は契約形態によって異なります。
たとえば、被保険者が夫で、保険料を支払う契約者と満期保険金の受取人も夫のケースなど、保険料を支払う契約者と受取人が同一の場合、所得税の対象です。被保険者が妻で、契約者と受取人が夫の場合も同様です。
被保険者と契約者が夫で、満期保険金の受取人が妻のケースなど、契約者と受取人が異なる場合は、満期保険金を贈与するとみなされ、贈与税がかかります。被保険者が妻で、契約者が夫、受取人が妻のケースや、被保険者が妻で、契約者が夫、受取人が子どもといったケースも該当します。
所得税が課税される場合の計算方法
養老保険の満期保険金に所得税が課税されるケースでは、満期保険金は一時所得という扱いになります。一時所得は、「満期保険金-払込済み保険料の総額-特別控除50万円」という方法で算出します。また、課税所得は、一時所得の1/2です。
満期保険金が500万円、払込済み保険料の総額が440万円というケースを例に挙げます。
例)500万円-440万円-50万円=10万円 一時所得10万円
10万円×1/2=5万円 課税所得5万円
この例では、一時所得の5万円とほかの所得を合わせた合計所得金額に、所得税の税率をかけて所得税を算出します。
特別控除の50万円があるため、ほかに一時所得がない場合、満期保険金と払込済み保険料の総額の差額が50万円を超えなければ、所得税の課税の対象になりません。また、サラリーマンなどの給与所得者は、給与が2,000万円を超えてなく、給与を1か所のみからもらっている人は、給与所得以外の所得が20万円を超えていなければ、確定申告の義務は発生しません。
ただし、5年未満の保険期間の一時払い養老保険は金融類似商品にあたり、満期保険金から払込済み保険料の総額を引いた利益に対して、20.315%の源泉分離課税が源泉徴収されます。一時払い養老保険を5年以内に解約した場合の解約返戻金も同様の扱いです。
贈与税が課税される場合の計算方法
養老保険の満期保険金に贈与税が課税されるケースでは、贈与税の基礎控除の110万円を引くことはできますが、払込済み保険料の総額は控除できません。その年にほかに贈与を受けていなければ、満期保険金から110万円を引いた金額に贈与税が課税されます。
所得税の対象となるケースと同様に、500万円の満期保険金を受け取った場合を例に挙げていきます。
例)500万円-110万円=390万円 課税所得390万円
200万円×10%+100万円×15%+90万円×20%=53万円 一般贈与の場合
贈与税は20歳以上の子や孫など直系尊属への特例贈与と、それ以外の一般贈与では税率が異なり、夫婦間の贈与の場合は一般贈与です。被保険者と契約者が夫で、満期保険金の受取人が妻のケースに当てはめると、53万円もの贈与税がかかります。
養老保険は多くのケースで、贈与税の課税対象になると税務上不利ですので、保険料の支払いをする契約者や保険金受取人を誰にするか慎重に判断しましょう。
こちらの記事では満期保険金にかかる税金について計算式を使って紹介しています。ケース別に紹介しているので参考にしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
養老保険は終身保険と同様に、必ず保険金を受け取ることができる生命保険で、死亡保険金と満期保険金が同額なのが大きな特徴です。相続税対策には終身保険が向いていますが、将来決まった時期にまとまったお金が必要な場合は、養老保険も検討対象になります。養老保険などさまざまな保険から、ライフプランに合った保険商品を選びましょう。