医療保険や介護保障保険などに加入している場合、介護医療保険料控除を利用すると所得税や住民税が安くなることを知っていますか?この記事では、介護医療保険料控除とは何か、計算方法や申請の仕方・書類の書き方などをわかりやすく解説します。
目次
介護医療保険料控除とは?
介護医療保険料控除は2012年の税制改正によって新設された制度です。それ以前は一般生命保険料控除・個人年金保険料控除のみが控除項目となっていましたが、改正に伴って新設されました。
一般生命保険料・個人年金保険料と同様に、介護医療保険料も年末調整や確定申告で申告を行うと所得控除を受けることができます。年末調整時に申告ができなかった場合、確定申告を行うことで控除が適用されます。
生命保険料控除のひとつ
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3点をまとめて、広義の「生命保険料控除」と呼んでいます。狭義の場合、生命保険料控除は「一般生命保険料控除」のみを指すため、注意してください。
また税制改正に伴い、広義の「生命保険料控除」では適用される保険料の範囲や控除額が旧制度と新制度で異なるため注意しましょう。2011年12月31日以前に加入した保険は旧制度が適用され、最大で5万円の控除となります。2012年1月1日以降に加入した保険は新制度の対象となり、最大で4万円が控除されるようになりました。介護医療保険料控除は新設された制度であるため、新制度のみが適用されます。
医療保険などが対象
介護医療保険控除の対象となるのは、2012年1月1日以降に加入した医療保険・医療費用保険・がん保険・介護保障保険・介護費用保険の保険料です。「入院や通院などを伴う疾病・身体障害に備える保険の主契約・特約部分の保険料が対象になる」と覚えておくといいでしょう。
そのため、貯蓄型保険や傷害保険などは原則として対象外となっています。また、海外の生命保険会社と国外で契約したものや、5年未満の保険期間のものも対象とされていません。公的な介護保険料についても介護医療保険料控除の対象とはならず、社会保険料控除の対象となります。
生命保険料控除については、こちらの記事も参照してください。
確定申告で受けられる生命保険料控除とは?家族の分も対象になる?
計算方法や控除額の上限は?
介護医療保険控除額を算出する手順は次の通りです。
まず、加入している医療保険や介護保障保険などの年間の払込保険料を計算しましょう。次に、所得税・住民税の控除額を算出します。介護医療保険料控除は新設された制度であるため、新制度に沿って計算を行います。
所得税
所得税の控除額は以下のように計算します。
年間の払込保険料が20,000円以下…全額控除
払込保険料が20,000〜40,000円以下…(年間正味払込保険料×1/2)+10,000円
払込保険料が40,000〜80,000円以下…(年間正味払込保険料×1/4)+20,000円
払込保険料が80,000円以上…一律40,000円
つまり、もし年間で10万円の保険料を払い込んでいたとしても、控除額は40,000円となります。
住民税
一方、住民税の控除額は以下の通り計算します。
年間の払込保険料が12,000円以下…全額控除
払込保険料が12,000〜32,000円以下…(年間正味払込保険料×1/2)+6,000円
払込保険料が32,000〜56,000円以下…(年間正味払込保険料×1/4)+14,000円
払込保険料が56,000円以上…一律28,000円
こちらも、もし8万円の保険料を払い込んでいても控除は28,000円となります。
注意しなければならないのは、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の控除額の合計には上限が設けられているという点です。所得税における控除限度額は合計12万円まで、住民税における控除限度額は合計7万円までとなっています。また、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除に該当する保険の中で2011年12月31日より以前に加入したものは更新のタイミングで新制度に切り替わるため、覚えておきましょう。
医療保険の控除については、こちらの記事にも詳しくまとめてあります。
医療保険は控除を受けられる?上限や計算式を解説
介護医療保険料控除を受けるには?
続いて、介護医療保険料控除を受けるための手続きや必要書類などを見ていきましょう。介護医療保険料控除を受けるには、「生命保険料控除」の申告を行う必要があります。
年末調整か確定申告が必要
会社に所属して給与の支払いを受けている人(会社員など)は年末調整で申告を行います。年末調整の時期になると会社から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配布されるため、必要事項の記入を行いましょう。生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」とともに会社へ提出すれば、以降の手続きは原則として必要ありません。
フリーランサー・自営業者などは、確定申告を行います。確定申告書B第一表・第二表に記入し、「生命保険料控除証明書」「源泉徴収票」とともに税務省へ提出してください。確定申告書B第一表では生命保険料控除の行へ、第二表では生命保険料控除の欄へそれぞれの金額を記入しましょう。
生命保険料控除証明書が必要
生命保険料控除証明書は、年末調整・確定申告どちらを行う場合にも必要となります。生命保険料控除証明書は10〜11月ごろに保険会社から自宅へハガキで送られてくるため、特別な交付手続きなどをする必要はありません。紛失してしまった場合、保険会社に連絡をすれば再発行が可能です。介護医療保険料控除の手続きで使用するのは「介護医療用」と書かれた証明書ですので、書面を確認しておきましょう。
年末調整や確定申告の注意点
年末調整を行えなかった場合、確定申告によって控除の手続きをすることができます。再年末調整ができることもありますが、会社によるため注意しましょう。また、節税対策で還付申告をする場合、過去5年以内に限って申告が可能です。控除漏れがあった年の翌年から5年間は、確定申告の期限に関係なく確定申告書を提出することができます。
年末調整の書類の書き方は?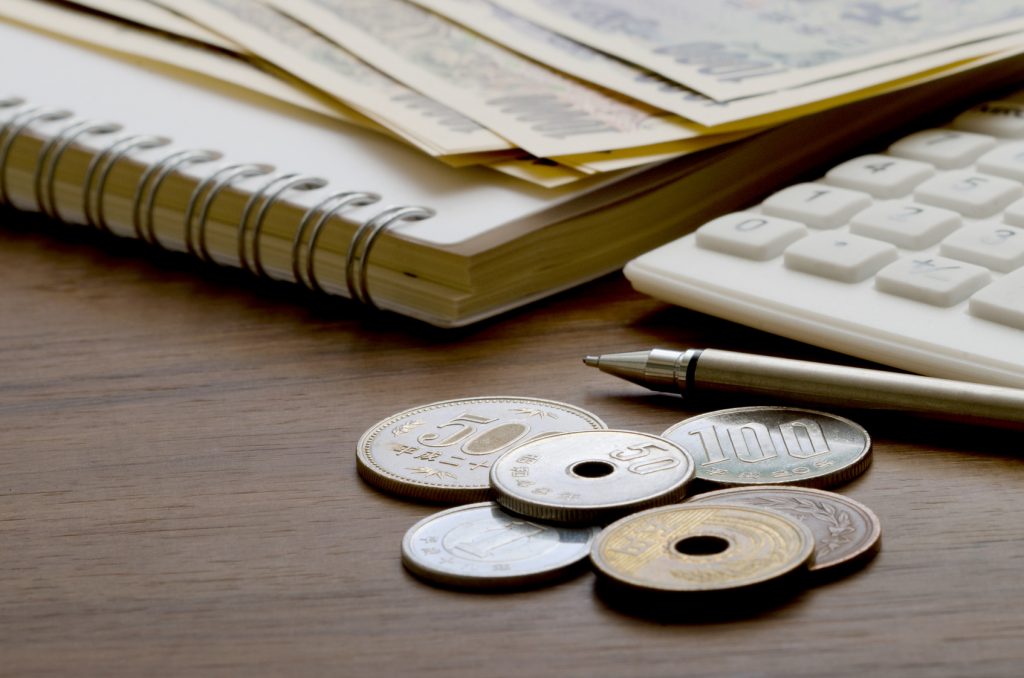
生命保険料控除証明書には、証明額と「ご参考」という欄に書いてある金額の2種類があります。「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、「ご参考」に記載されている申告額を記入します。証明額は証明書が交付された月までの金額ですが、申告が必要となる金額は年間の払込保険料総額であるため、間違いのないようにしましょう。
「介護医療保険料」の欄に記入
年間払込金額や控除金額を記入するのは「介護医療保険料」の欄です。誤って「一般の生命保険料」や「個人年金保険料」の欄へ記入しないように注意しましょう。先ほど説明した通り、介護保険料控除金額は最大で40,000円です。
その他に、保険会社名・保険の種類(介護保障保険やがん保険など)・保険期間・契約者氏名・受取人氏名と続柄・確認印の記載が必要となるため、漏れのないように気をつけて下さい。これらの事項は生命保険料控除証明書に記載されているので、証明書を見ながら転記するとよいでしょう。ただし、証明書には受取人に関しての記載はないため、保険証券を確認してください。
生命保険料控除の確定申告については、こちらの記事もご覧ください。
確定申告で生命保険料控除を受けるには?計算方法と書き方を解説
確定申告書への書き方は?
確定申告で控除の申請をする場合、必要になる書類は
・確定申告書A第一表・第二表もしくはB第一表・第二表
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
の3点です。印鑑も忘れずに用意しておきましょう。また、2016年から開始したマイナンバー制度により、確定申告書にもマイナンバーの記載が必要となりました。確定申告書を提出する際にも本人確認書類として、マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類の提示(コピーの添付でも可)を求められることがあります。マイナンバーカードを持っていない人、紛失してしまった人はすみやかに発行しておくと安心です。
会社員の人は確定申告書A第一表・第二表、フリーランサーや自営業者は確定申告書B第一表・第二表を使用します。確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードしてください。
保険料を記入し税額を計算
確定申告書A・Bともに第一表へは介護医療保険料控除金額、第二表へは年間払込料の金額を記入します。その他の箇所は源泉徴収票の内容を転記していくとスムーズです。
まず第二表に、介護医療保険料控除に該当する保険の年間払込保険料を「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「生命保険料控除」欄へ記入します。算出した控除金額は第一表の「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」へ記入し、「税金の計算」内の「課税される所得金額」を算出します。下部に税額を記入する箇所があるため、そちらも忘れないようにしましょう。
税額の計算式は「課税される所得金額×税率−所得税の控除額」となっており、課税される所得金額によって所得税の税率が異なります。例えば「課税される所得金額」が195〜330万円以下の場合、その金額に税率の10%をかけ、算出された金額から所得税控除額の97,500円を引いた金額が税額になります。
課税される所得金額ごとの税率と所得税控除額は以下の通りです。
| 所得金額 | 税率 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
夫婦の介護医療保険控除はどうなる?
夫婦ふたりとも、もしくは家族が医療保険や介護保障保険に加入している場合、介護医療保険料控除の対象者は誰になるのでしょうか?以下で説明します。
被扶養者は原則的に自分で控除申請ができない
収入のない被扶養者は年末調整や確定申告をする必要がないため、自分で介護医療保険料控除の申請を行うことはできません。また、働いていても収入が扶養範囲内である人も同じ理由により自分で申請は行えません。
妻の保険料を夫が払えば控除対象
会社員でがん保険に加入している夫、主婦で医療保険に加入している妻がいると仮定しましょう。年末調整や確定申告を行えない妻に代わって、夫が妻の分も控除申告をすることは可能です。ただし、妻の医療保険の保険料を夫が払い込んでいることが条件となります。
介護医療保険料控除に限らず、生命保険料控除全体において「保険金の受取人は保険料の払い込みをする人と同一であるか、その配偶者や親族でなければならない(個人年金保険料控除の場合、親族は含まれない)」と規定されていますが、契約者に関しては決まりがありません。よって、契約者と保険料の払い込み者が同一でなくても医療保険控除を受けることができます。その際、控除の対象となるのは保険料の払い込みをしている人となります。
通例では契約者が保険料の払い込みをしますが、夫が払い込んだことを明らかにできれば問題はありません。また、親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)の保険料を夫が払い込んでいるケースについても同様です。この場合、親族が夫と生計を一にしていなくても控除が適用されます。
共働きに有利な契約形態とは
共働きの夫婦でそれぞれが保険に加入している場合、夫がすべての保険料を支払うのでなく、妻が自分の保険料を払い込み、控除申請をした方が得をするケースもあります。
夫が自分の介護医療保険料控除(もしくは生命保険料控除)の限度額に達してしまっているときなどは、妻が保険の契約者となって保険料の払い込みや控除申請を行うことで控除額を増やすことが可能となる場合があります。保険の契約者を決める際、このような観点から考えてみるのも一つの方法といえます。
まとめ
介護医療保険料控除の手続きは、ポイントを抑えればそれほど難しいものではありません。控除額の上限や書類への記入の仕方、控除の対象者などに注意して、制度を有効に活用しましょう。不明点や不安がある場合、保険代理店などで手続きを教えてもらえることもあります。保険相談と同時にたずねてみてもよいかもしれません。
保険以外の相談もOK!わかりやすい説明付きの無料相談サービス実施中!



