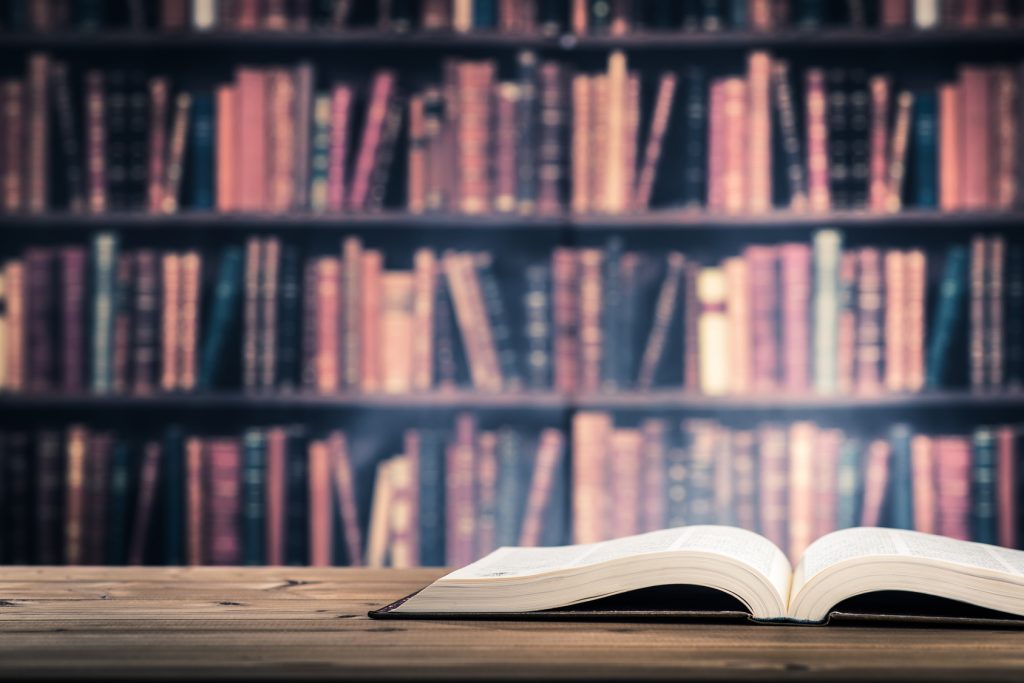子どもの誕生とともに多くの人が加入する学資保険ですが、生命保険料控除を受けられることを知っていますか。この記事では学資保険控除の申告方法や税金がいくら控除されるか、そして学資保険に必ず入るべきかなどについて解説します。学資保険選びの参考にしてください。
目次
学資保険は生命保険料控除が利用できる?
学資保険は一般生命保険料控除に区分
学資保険の保険料は「一般生命保険料控除」の対象となります。生命保険料控除は、契約時期によって下記のように分類されます。受けられる控除の金額にも違いがあるため、加入している学資保険の契約時期を確認してみるとよいでしょう。
平成24年1月1日以前の契約(以下、「旧制度」)では「旧一般生命保険料控除」と「旧個人年金保険料控除」の2つがあり、それぞれ年間5万円まで控除可能です。また、平成24年1月1日以降の契約(以下、「新制度」)に関しては、「新一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」の3つに分けられます。新制度ではそれぞれ年間4万円まで控除を受けることができます。
税金のうち所得税と住民税が対象
生命保険料控除の目的は、個人ごとの事情を加味した税額を算出することです。各種所得の合計金額から控除額が差し引かれることで税金額が各々の所得に応じたものとなり、税金の負担が軽減されます。
その他にも、雑損控除や社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除が設けられており、確定申告や年末調整などで控除を受けられる仕組みになっています。生命保険料については所得税と住民税の2点が控除の対象となっており、それぞれの金額も異なっているため、税額の計算時には注意が必要です。
確定申告については確定申告で生命保険料控除を受けるには?計算方法と書き方を解説でも詳しく紹介しています。
学資保険控除はいくら?計算方法は?
所得税
年間払込保険料額によって控除額は異なりますが、計算方法は以下の通りです。新制度では最大4万円まで控除を受けることができます。
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 20,000~40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,000~80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
同様に、旧制度では最大5万円まで控除を受けることができます。
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 25,000~50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,000~100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税
所得税と同じく、控除額は年間払込保険料額によりますが、新制度で最大2万8千円まで控除を受けることができます。
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 12,000~32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
| 32,000~56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律 28,000円 |
旧制度での最大控除額は、3万5千円です。
| 年間払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 15,000~40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
| 40,000~70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
上限まで利用していると適用外
学資保険のみについて言うと、保険料控除額の上限は新制度であれば所得税4万円、住民税2万8千円の合計6万8千円となります。旧制度であれば所得税5万円、住民税3万5千円の合計8万5千円です。
しかし、ここに通常の生命保険の保険料を加えても、限度額を超えて控除額を増やすことはできません。新制度・旧制度ともにそれぞれ保険料控除の分野が決められているためです。保険会社から発行される保険料控除の内訳明細を見ればそれぞれの分野で利用できる金額が記載されていますので、一度確認してみましょう。
生命保険料控除の申告方法
サラリーマンは年末調整
企業に勤めているサラリーマンにとっては、12月が年末調整の時期にあたります。多くの場合、年間払込保険料が記載された通知を提出すれば会社が残りの手続きを代行してくれます。
基礎控除や配偶者控除などの計算や手続きについても同様で、保険料払込通知書と記入済みの保険料控除申告書を会社へ提出すれば年末調整に関する作業は完了となります。
個人事業主は確定申告
給与所得者ではない自営業者は、毎年2月~3月にかけて確定申告を行う必要があります。記入内容については国税庁のHPやe-Taxなどを参考にしてみるとよいでしょう。確定申告書と生命保険料控除申告書を一緒に提出すると控除を受けることができます。確定申告の生命保険料控除については確定申告で受けられる生命保険料控除とは?家族の分も対象になる?でも解説しています。
学資保険は必ず入らなければいけない?
貯蓄と保障が得られるものもある
商品や保険会社によっては、契約者が死亡あるいは高度障害と診断されたときに保険料の払込が免除される「払込免除特約」を付加できるものがあります。払込免除特約を付加した場合、保険料の払込が免除されるだけでなく保障も継続されるため、契約者に万が一のことがあっても子どもの教育資金を確保できます。学資保険は貯蓄だけでなく保障も得られる商品だといえるでしょう。
ただし、払込免除特約の付加ができない学資保険もあります。
他に貯める方法があれば絶対ではない
子どもの教育資金を貯める方法は学資保険だけではありません。例えば、銀行の定期預金や終身保険を学資保険の代わりに加入する方法もあります。学資保険は学資金の受取があらかじめ決められていますが、学資保険に比べて終身保険は保険金の受取が柔軟に決められます。学資保険と終身保険については、学資保険と終身保険、教育資金におすすめはどっち?メリットを比較!で解説しています。
家庭によってライフプランは異なります。場合によっては学資保険に限定せず、家庭の状況にあった方法で学資金を貯めても良いかもしれません。学資保険の必要性については学資保険とは?入る必要性はある?返戻率をチェックして選ぼうや学資保険の評判をリアルな口コミからチェック!加入する必要はある?も参考にしてください。
まとめ
教育資金を効率よく積み立てることができる学資保険では、生命保険料控除を受けることができます。所得税と住民税からの控除を受けることができるのは大きなメリットと言え、節税効果もあります。学資保険について正しく知り、効率的な節税や積立を目指してみてはいかがでしょうか。